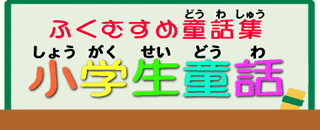| メ ニ ュ ー 福娘童話集 |
| ・4年生の日本昔話 |
| ・4年生の世界昔話 |
| ・4年生の日本みんわ |
| ・4年生のイソップ童話 |
| ・4年生のえど こばなし |
| ・小学生童話へ |
4年生の日本昔話
耳なし芳一(ほういち)
※本作品は、読者からの投稿作品です。 投稿希望は、メールをお送りください。→連絡先
投稿者 「りっきぃの夜話」 りっきぃの夜話
| ♪音声配信(html5) |
| 音声 ; 創作活動のサイト 『Web団 零点』 |
| ♪音声配信(html5) |
| 音声 ; 田布施座 |
むかしむかし、いまの下関(しものせき→山口県)に、阿弥陀寺(あみだじ→真言宗(しんごんしゅう)の寺)というお寺がありました。
その寺に、芳一(ほういち)という、びわひきがおりました。
芳一(ほういち)は、おさないころから目が不自由(ふじゆう)だったために、びわのひき語りをしこまれ、まだほんの若者(わかもの)ながら、そのうでまえは、ししょうの和尚(おしょう)さんをしのぐほどになっていました。
阿弥陀寺(あみだじ)の和尚(おしょう)さんは、そんな芳一(ほういち)の才能(さいのう)を見こんで、寺にひきとったのでした。
芳一(ほういち)は、源平(げんぺい)の物語を語るのがとくいで、とりわけ、壇ノ浦(だんのうら)の合戦(かっせん)のくだりのところでは、その真にせまった語り口に、だれ一人、なみだをさそわれないものはいなかったそうです。
そのむかし、壇ノ浦(だんのうら)で、源氏(げんじ)と平家の長いあらそいの、さいごの決戦(けっせん)がおこなわれ、戦(たたか)いにやぶれた平家一門は、女や子どもにいたるまで、安徳天皇(あんとくてんのう)として知られている幼帝(ようてい)もろとも、ことごとく海の底(そこ)にしずんでしまいました。
この、悲しい平家のさいごの戦(たたか)いを語ったものが、壇ノ浦(だんのうら)の合戦(かっせん)のくだりなのです。
ある、むしあつい夏の夜のことです。
和尚(おしょう)さんが、法事(ほうじ)で出かけてしまったので、芳一(ほういち)は、一人でお寺にのこってびわのけいこをしておりました。
そのとき、庭の草がサワサワと波のようにゆれて、えんがわにすわっている芳一(ほういち)の前でとまりました。
そして、声がしました。
「芳一(ほういち)! 芳一(ほういち)!」
「はっ、はい。どなたさまでしょうか? わたしは、目が見えませんもので」
すると、声の主はこたえます。
「わしは、この近くにお住まいの、さる身分の高いお方の使いの者じゃ。殿(との)が、そなたのびわと語りを聞いてみたいとおのぞみじゃ」
「えっ、わたしのびわを?」
「さよう、やかたへ案内(あんない)するから、わしのあとについてまいれ」
芳一(ほういち)は、身分の高いお方が、自分のびわを聞きたいとのぞんでおられると聞いて、すっかりうれしくなって、その使いの者についていきました。
歩くたびに、ガシャツ、ガシャツと、音がして、使いの者は、よろいで身をかためている武者(むしゃ)だとわかります。
門をくぐり、広い庭をとおると、大きなやかたの中にとおされました。
そこは大広間で、おおぜいの人が集まっているらしく、サラサラときぬずれの音や、よろいのふれあう音が聞こえていました。
一人の女官(じょかん→宮中に仕える女性(じょせい))がいいました。
「芳一(ほういち)や、さっそく、そなたのびわにあわせて、平家の物語を語ってくだされ」
「はい。長い物語ゆえ、いずれのくだりをお聞かせしたらよろしいのでしょうか?」
「・・・壇ノ浦(だんのうら)のくだりを」
「かしこまりました」
芳一(ほういち)は、びわを鳴らして語りはじめました。
ろをあやつる音。
ふねにあたってくだける波。
弓鳴りの音。
兵士(へいし)たちの、おたけびの声。
息たえた武者(むしゃ)が、海に落ちる音。
これらのようすを、しずかにもの悲しく語りつづけます。
大広間は、たちまちのうちに壇ノ浦(だんのうら)の合戦場(かっせんば)になってしまったかのようでした。
やがて、平家の悲しいさいごのくだりになると、広間のあちこちから、むせびなきがおこり、芳一(ほういち)のびわが終わっても、しばらくはだれも口をきかず、シーンと、静(しず)まりかえっておりました。
やがて、さっきの女官(じょかん)がいいました。
「殿(との)もたいそうよろこんでおられます。よいものをおれいにくださるそうじゃ。されど、今夜より六日間、毎夜そなたのびわを聞きたいとおっしゃいます。あすの夜も、このやかたにまいられるように。それから寺へもどっても、このことはだれにも話してはならぬ、よろしいな」
「はい」
つぎの日も、芳一(ほういち)はむかえにきた武者(むしゃ)について、やかたにむかいました。
しかし、昨日(きのう)とおなじようにびわをひいて、寺にもどってきたところを、和尚(おしょう)さんに見つかってしまいました。
「芳一(ほういち)、いまごろまで、どこでなにをしていたんだね?」
「・・・・・・」
和尚(おしょう)さんがいくらたずねても、芳一(ほういち)は、やくそくを守って、ひとことも話しませんでした。
和尚(おしょう)さんは、芳一(ほういち)がなにもいわないのは、なにか深いわけがあるにちがいないと思いました。
そこで寺男(てらおとこ→寺の雑用係(ざつようがかり))たちに、芳一(ほういち)が出かけるようなことがあったら、そっとあとをつけるように、いっておいたのです。
そして、また夜になりました。
雨がはげしくふっています。
それでも、芳一(ほういち)は寺を出ていきます。
寺男たちは、そっと芳一(ほういち)のあとを追いかけました。
ところが、目が見えないはずの芳一(ほういち)の足は意外にはやく、やみ夜にかき消されるように、すがたが見えなくなってしまったのです。
「どこへいったんだ?」
と、あちこちさがしまわった寺男たちは、墓地(ぼち)へやってきました。
ビカッ!
いなびかりで、雨にぬれた墓石(ぼせき)がうかびあがります。
「あっ、あそこに!」
寺男たちは、おどろきのあまり立ちすくみました。
雨でずぶぬれになった芳一(ほういち)が、安徳天皇(あんとくてんのう)の墓(はか)の前で、びわをひいているのです。
その芳一(ほういち)のまわりを、無数(むすう)の鬼火(おにび)がとりかこんでいます。
寺男たちは、芳一(ほういち)が亡霊(ぼうれい)にとりつかれているにちがいないと、力まかせに寺へつれもどしました。
そのできごとを聞いた和尚(おしょう)さんは、芳一(ほういち)を亡霊(ぼうれい)から守るために、まよけのまじないをすることにしました。
そのまよけとは、芳一(ほういち)の体じゅうに、経文(きょうもん)をかきつけるのです。
「芳一(ほういち)、おまえの人なみはずれた芸(げい)が、亡霊(ぼうれい)をよぶことになってしまったようじゃ。無念(むねん)のなみだをのんで海にしずんでいった、平家一族のな。よく聞け。今夜はだれかがよびにきても、けっして口をきいてはならんぞ。亡霊(ぼうれい)にしたがった者は命をとられる。しっかり座禅(ざぜん)を組んで、身じろぎひとつせぬことじゃ。もし返事をしたり声をだせば、おまえはこんどこそ、ころされてしまうじゃろう。わかったな」
和尚(おしょう)さんはそういって、村のお通夜に出かけてしまいました。
芳一(ほういち)が座禅(ざぜん)をしていると、いつものように、亡霊(ぼうれい)の声がよびかけます。
「芳一(ほういち)、芳一(ほういち)、むかえにまいったぞ」
でも、芳一(ほういち)の声もすがたもありません。
亡霊(ぼうれい)は、寺の中へ入ってきました。
「ふむ。・・・びわはあるが、ひき手はおらんな」
あたりを見まわした亡霊(ぼうれい)は、ちゅうにういている二つの耳を見つけました。
「なるほど、和尚(おしょう)のしわざだな。さすがのわしでも、これでは手が出せぬ。しかたない、せめてこの耳を持ち帰って、芳一(ほういち)をよびにいったあかしとせねばなるまい」
亡霊(ぼうれい)は、芳一(ほういち)の耳に手をかけると、
バリッ!
その耳をもぎとって、帰っていきました。
そのあいだ、芳一(ほういち)はジッと、座禅(ざぜん)を組んだままでした。
寺にもどった和尚(おしょう)さんは、芳一(ほういち)のようすを見ようと、大いそぎで芳一(ほういち)のいるざしきへかけこみました。
「芳一(ほういち)! ぶじだったか!」
じっと座禅(ざぜん)を組んだままの芳一(ほういち)でしたが、その両の耳はなく、耳のあったところからは、血が流れています。
「お、おまえ、その耳は・・・」
和尚(おしょう)さんには、すべてのことがわかりました。
「そうであったか。耳に経文(きょうもん)を書きわすれたとは、気がつかなかった。なんと、かわいそうなことをしたものよ。よしよし、よい医者をたのんで、すぐにもきずの手当てをしてもらうとしよう」
芳一(ほういち)は両耳をとられてしまいましだが、それからはもう、亡霊(ぼうれい)につきまとわれることもなく、医者の手当てのおかげで、きずもなおっていきました。
やがて、この話は口から口へとつたわり、芳一(ほういち)のびわは、ますますひょうばんになっていきました。
びわ法師(ほうし)の芳一(ほういち)は、いつしか「耳なし芳一(ほういち)」とよばれるようになり、その名を知らない人はいないほど、ゆうめいになったということです。
おしまい
| 福娘のサイト 366日への旅 |
毎日の素敵な記念日をイラスト付きで紹介。 |
毎日の誕生花を花写真付きで紹介。 |
| きょうの誕生日・出来事 有名人の誕生日やその日の出来事と性格判断 |
| 福娘のサイト 子どもの病気相談所 |
| 子どもの病気相談所 病気検索と対応方法、症状から検索するWEB問診 |
| 福娘のサイト 世界60秒巡り |
| 世界60秒巡り 世界の国旗・国歌・国鳥・観光名所などを紹介。 |
| 世界遺産巡り 日本と世界の世界遺産を写真付きで紹介。 |
| 都道府県巡り 47都道府県の豆知識。 県章、県鳥、県花、観光名所など。 |