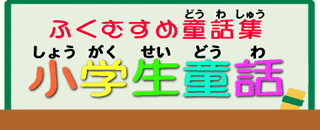| メ ニ ュ ー 福娘童話集 |
| ・4年生の日本昔話 |
| ・4年生の世界昔話 |
| ・4年生の日本みんわ |
| ・4年生のイソップ童話 |
| ・4年生のえど こばなし |
| ・小学生童話へ |
4年生の日本昔話
番町皿屋敷(ばんちょうさらやしき)
| ♪音声配信(html5) |
| 朗読者 ; スタヂオせんむ |
江戸(えど)の番町のあるおやしきに、おきくという、うつくしいこしもとがいました。
こしもととは、殿(との)さまの身のまわりのおせわをする女の人です。
おやしきには、いく人ものこしもとがいましたが、殿(との)さまの青山播磨(あおやまはりま)は、おきくが大のおきにいりです。
いつも、
「おきく、おきく」
と、かわいがっていました。
ほかのこしもとは、おもしろくありません。
そして、
「ふん、なによ。おきく、おきくって」
「おきくも、おきくよ。いいきになっちゃってさ」
「ねえ、ちょっと、こまらせてやろうよ」
と、わるいそうだんを始めました。
それは、殿(との)さまがだいじにしている、十まいひとくみの絵ざらを一まいかくして、おきくのせいにしてやろうというものです。
このおさらは、先祖(せんぞ)からつたわる家宝(かほう)で、一まいかけても、ねうちがなくなってしまいます。
ある日、ひさしぶりに絵ざらをながめようとすると、九まいしかありません。
さっそく、こしもとたちをよびつけて、しらべると、
「そのおさらなら、おきくが一まいわったのです」
だれもが口をそろえていうので、殿(との)さまは、おきくをきびしくしかりました。
「じぶんがわったならわったと、しょうじきにいえば、ゆるしてやる」
「いいえ、わたくしには、まったく身におぼえがございません。なにかのおまちがいです」
「えーい! かんだいにゆるしてやると言っておるのに、まだいいのがれをするつもりか!」
「でも、わたくしは、なにもしりません」
「まだ言うか! 顔もみとうない! 出て行け!」
かわいそうに、おきくはその晩(ばん)、やしきの井戸(いど)に身を投げて、死んでしまいました。
さて、それからというもの、まよなかになると、やしきの井戸(いど)のなかから、
「一まーい、二まーい、三まーい、四まーい、五まーい、六まーい、七まーい、八まーい、九まーい、・・・ああ、うらめしやぁ」
あわれきわまりないこえで、おさらをかぞえるようになりました。
それからというもの、おやしきにはよくないことがつづいて、殿(との)さまもこしもとたちも、つぎつぎと死んでしまいました。
※岡本綺堂(おかもときどう)の戯曲(ぎきょく)。1916年(大正5)初演(しょえん)では、お菊(きく)が恋仲(こいなか)の青山播磨(あおやまはりま)の気持ちをためそうと、自分で家宝(かほう)の皿を割(わ)ったことになっています。
おしまい
| 福娘のサイト 366日への旅 |
毎日の素敵な記念日をイラスト付きで紹介。 |
毎日の誕生花を花写真付きで紹介。 |
| きょうの誕生日・出来事 有名人の誕生日やその日の出来事と性格判断 |
| 福娘のサイト 子どもの病気相談所 |
| 子どもの病気相談所 病気検索と対応方法、症状から検索するWEB問診 |
| 福娘のサイト 世界60秒巡り |
| 世界60秒巡り 世界の国旗・国歌・国鳥・観光名所などを紹介。 |
| 世界遺産巡り 日本と世界の世界遺産を写真付きで紹介。 |
| 都道府県巡り 47都道府県の豆知識。 県章、県鳥、県花、観光名所など。 |