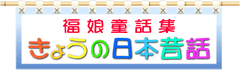
福娘童話集 > きょうの日本昔話 > 8月の日本昔話 > 百ものがたりのゆうれい
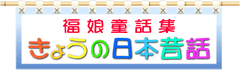
福娘童話集 > きょうの日本昔話 > 8月の日本昔話 > 百ものがたりのゆうれい
8月9日の日本の昔話
百物語のゆうれい
むかしむかし、ある村で、おそうしきがありました。
ひるまにおおぜい集まった、おとむらいの人たちも、夕方にはすくなくなって、七、八人のわかものがのこっただけになりました。
「せっかく集まったんだ。寺のお堂をかりて、『百物語(ひゃくものがたり→詳細)』をやってみねえか?」
ひとりがいいだすと、
「いや、おとむらいのあとで、『百物語』をすると、ほんとうのおばけがでるっていうぞ。やめておこう」
ひとりが、しりごみしました。
『百物語』と、いうのは、夜おそくにみんなで集まって、百本のローソクに火をつけ、おばけの話しをすることです。
はなしがおわるたびに、ひとつ、またひとつと、ローソクの火をけしていき、さいごのローソクがきえると、ほんとうのおばけがでるということですが、わかものたちは、まだためしていません。
「いくじなしめ。ほんとうにおばけがでるかどうか、やってみなくちゃわかるまい」
「そうだ、そうだ」
「よし、やってみるべえ」
と、いうことになりました。
わかものたちは寺のお堂で、『百物語』をはじめました。
みんなでかわるがわる、おばけのはなしをしていって、ローソクの火をひとつひとつ、けしていきます。
夜もしだいにふけて、ローソクの火も、とうとう、あとひとつになりました。
はじめのうちこそ、おもしろはんぶんでいたわかものたちも、しだいにこわくなってきました。
「いいか、このさいごのローソクがきえたら、ほんとのおばけがでるかもしれん。だが、どんなおばけがでようと、おたがいに、にげっこなしにしよう」
「いいとも。どんなおばけがでるか、この目で、しっかりみてやろう」
わかものたちは口ぐちにいいましたが、『百物語』の百番目のはなしがおわって、さいごのローソクの火がけされると、まっくらなお堂から、ひとりにげ、ふたりにげして、のこったのは、たったひとりでした。
のこったわかものがどきょうをすえて、くらやみのお堂にすわっていると、
♪ヒュー、ドロドロドロドロー。
目の前に、白いきもののゆうれいがあらわれました。
「う、・・・うらめしやー」
わかものは思わず、逃げ出しそうになりましたが、よくみると、ほれぼれするような美人のゆうれいです。
「これは、かなりのべっぴんさんだ」
あいてがゆうれいでも、わかくてきれいな美人ゆうれいだと、少しもこわくありません。
わかものはすわりなおすと、ゆうれいにききました。
「うらめしいといったが、なにがうらめしいのだ。『うらめしやー』といわれただけでは、なんのことかわからん。これもなにかのえんだ。わけをきかせてくれないか」
すると、ゆうれいがしおらしく、
「はい、よくぞたずねてくださいました。わたしは、山むこうの村からこちらの村の庄屋(しょうや→詳細)さまのところにやとわれたものですが、ふとしたやまいで、いのちをおとしました。けれど、庄屋さまはお金をおしんで、おとむらいをだしてくれないのです。それでいまだに、あのよへゆけないでいるのです」
「なるほど、それは気のどくだ」
「こんや、みなさんがたが、『百物語』をしてくださったおかげで、ようやくお堂にでることができました。どうか、お寺の和尚(おしょう→詳細)さんにおねがいして、お経をあげてください。そうすれば、あの世へゆくことができます」
女のゆうれいは、わかものに手をあわせました。
「わかった。たしかにひきうけた」
わかものがこたえると、女のゆうれいはスーッときえていきました。
わかものはつぎの朝、和尚さんにわけをはなして、お経をあげてもらいました。
それからというもの、わかものは幸運つづきで、やがてたいした長者(ちょうじゃ→詳細)になったということです。
おしまい