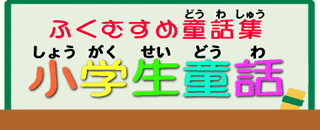| メ ニ ュ ー 福娘童話集 |
| ・6年生の日本昔話 |
| ・6年生の世界昔話 |
| ・6年生の日本民話 |
| ・6年生のイソップ童話 |
| ・6年生の えど 小話 |
| ・小学生童話へ |
6年生の日本民話
身投げ石
大分県の民話
むかしむかし、豊後の国(ぶんごのくに→大分県)に、岡の殿(おかのとの)という豪族(ごうぞく)が住んでいました。
岡の殿(おかのとの)には、大変美しい姫(ひめ)がいましたが、姫(ひめ)は重い病にかかってしまったのです。
「姫(ひめ)が不憫(ふびん→かわいそう)でならぬ、何としてもなおせ」
岡の殿(おかのとの)は家来たちに命令しましたが、しかし、どんな薬をあたえても、姫(ひめ)の病気には効かないのです。
姫(ひめ)の病気は、日に日に悪くなるばかりでした。
そんな、ある日の事。
どこからか一人のお坊(ぼう)さんがやって来て、岡の殿(おかのとの)に言いました。
「不治(ふじ)の病には 黒い花の咲(さ)くユリの根を煎(せん)じて飲ますとよいと、聞きおよびます。しかし、そのようなユリの花がどこにあるのやら」
岡の殿(おかのとの)は、あちこちにおふれを出しました。
《黒い花の咲(さ)くユリの花を探し出(さがしだ)した者には、姫(ひめ)を嫁(よめ)にとらす。一刻(いっこく)も早く探し出(さがしだ)せ》
それを読んだ人々は、山も川も海も、草の根を分けるようにして探(さが)しましたが、けれども、黒い花の咲(さ)くユリを見つけることは出来ませんでした。
「ええい、どこを探(さが)しておる。もっとよく探(さが)せ!」
しかし、やっぱりどこにも見つかりません。
屋敷(やしき)の人々があきらめかけたとき、岡の殿(おかのとの)がかわいがっていた栗毛(くりげ)のウマが、激(はげ)しくいなないて屋敷(やしき)にかけ込(こ)んできたのです。
そのウマの口には、なんと黒いユリの花が一本くわえられています。
岡の殿(おかのとの)は夢中で栗毛(くりげ)にまたがると、栗毛(くりげ)は矢のようにかけ出しました。
そしていくつもの山をこえた栗毛(くりげ)は、やがて深い谷で止まりました。
そこの岩間には、黒いユリの花が何本も咲(さ)いていたのです。
それからほどなくして、ユリの根を煎(せん)じて飲んだ姫(ひめ)は、元気になっていきました。
さて、黒い花の咲(さ)くユリを見つけてきた物には、姫(ひめ)を嫁(よめ)にやるという約束でしたが、相手がウマではどうしようもありません。
ところが、あの栗毛(くりげ)はその約束を知っているのか、いつも姫(ひめ)に寄りそっていて、姫(ひめ)の側を離(はな)れようとしないのです。
岡の殿(おかのとの)も姫(ひめ)も気味悪くなり、栗毛(くりげ)をウマ小屋に閉じ込(とじこ)めてしまいました。
しばらくたち、姫(ひめ)は病気全快のお礼参りに、八幡宮(はちまんぐう→八幡神(やはたかみ)を祭神とする神社の総称(そうしょう)へ詣(もう)でました。
ところが、カゴにのって帰る途中(とちゅう)、ウマ小屋から逃(に)げだした栗毛(くりげ)が、狂(くる)ったように姫(ひめ)の行列めがけて走ってきたのです。
「あっ、あぶない!」
「姫(ひめ)のお身を守れ!」
お供(とも)の者たちが姫(ひめ)を守ろうとしましたが、栗毛(くりげ)はお供(とも)の者たちを蹴散(けち)らすと、とうとう姫(ひめ)を、川に突(つ)き出た大きな岩の上に追いつめてしまったのです。
岩の下では川の濁流(だくりゅう)が、ゴウゴウ音をたてて流れています。
栗毛(くりげ)の目は怒(いか)りに燃えており、姫(ひめ)に一歩一歩近づいていきます。
「いやじゃあ!」
姫(ひめ)は叫び声(さけびごえ)をあげましたが、栗毛(くりげ)は姫(ひめ)を道連れに、川へ身を投げたのです。
いつのころからか、身投げ石と呼(よ)ばれるようになったその大岩は、栗毛(くりげ)のひづめのあとを今も残しているという事です。
おしまい
| 福娘のサイト 366日への旅 |
毎日の素敵な記念日をイラスト付きで紹介。 |
毎日の誕生花を花写真付きで紹介。 |
| きょうの誕生日・出来事 有名人の誕生日やその日の出来事と性格判断 |
| 福娘のサイト 子どもの病気相談所 |
| 子どもの病気相談所 病気検索と対応方法、症状から検索するWEB問診 |
| 福娘のサイト 世界60秒巡り |
| 世界60秒巡り 世界の国旗・国歌・国鳥・観光名所などを紹介。 |
| 世界遺産巡り 日本と世界の世界遺産を写真付きで紹介。 |
| 都道府県巡り 47都道府県の豆知識。 県章、県鳥、県花、観光名所など。 |