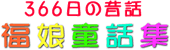| お話しの移動 |
| ・ 福娘童話集 ・ ジャンル別 ・ 日本の恩返し話 (全30話) → 1話 〜 10話 → 11話 〜 20話 → 21話 〜 30話 |
日本の恩返し話 第8話
かじかびょうぶ
むかしむかし、古くからさかえた家がありました。
ところがその家のいまの主人は、菊三郎(きくさぶろう)といって、生まれつきのなまけものです。
ノラリクラリとあそんでくらすうちに、たくさんの山や畑も売りつくして、とうとうさいごにのこった、おくの山を売らないといけないようになってしまいました。
それである日、そのおくの山を見にのぼっていきました。
谷川をどこまでもどこまでものぼっていって、きれいな流れになるあたりいったいが、菊三郎の持ち山です。
山には、天にもとどくような杉の木が、谷をはさんで、あっちの山にもこっちの山にも、何千本としげっています。
足もとはと見れば、みどりのこけがビッシリとはえ、谷川の水はつめたくすきとおって、なんとも美しい山でした。
それにこのあたりの谷川には、かじか(→カエルの一種。谷川の岩間にすみ、色は暗褐色でオスは美声で鳴きます)がたくさんすんでいて、とてもいい声で鳴きます。
それで人はみんな、かじか沢とよんでいました。
さて菊三郎は、そのかじか沢を、のぼったりくだったりしながら、この山を売ろうか、あの山を売ろうかと考えていましたが、すっかりくたびれてしまいました。
「どれ。一ねむりしようか」
菊三郎は、大きな一枚岩の上にひっくりかえりました。
杉木立(すぎこだち)のあいだの、青い空が目にしみるように美しく、かじかの美声が谷の底からわきあがるように聞こえてきます。
(気のせいか、きょうのかじかは、なにやらものかなしげに鳴いとるのう)
そんなことを考えているうちに、ウトウトと、ねむってしまいました。
「だんなさま、だんなさま」
どこからともなく、しわがれた声が聞こえてきます。
「菊三郎さま」
名まえをよばれてからだをおこすと、すぐ目の前に、きみょうな顔をしたおじいさんがひとり、すわっていました。
カエルみたいな顔で、着物のすそからは、しずくがポタポタとたれています。
「のう、菊三郎さま。おねげえでござります。このかじか沢だけは、どうか売らんでいてくださりませ。おたのみもうしますだ」
「そういう、おまえさんは?」
「へえ、もうしおくれまして。わっしゃ、このあたりいったいにすむ、かじかの頭領(とうりょう→親分)でごぜえます。だんなさまが、このかじか沢をお売りなさるってんで、あわててやってきました。なにとぞ、このかじか沢をお売りにならんよう、おねげえもうしますだ」
頭領はにじりよって、菊三郎の手をとってあたまを下げました。
その手の、なんとつめたいことでしょう。
そこで、菊三郎はハッと目がさめました。
「いまのは、ゆめだったのか」
と、てのひらをみてみれば、びっしょりと水でぬれています。
あまりのふしぎさに、菊三郎はもう山を見る気もしなくなって、そのまま家にかえりました。
山からかえると、菊三郎は、なんとかしてかじか沢は売らずにすませたい、そればかりを考えるようになりました。
それで、売りのこした古いかけ軸やら道具なんかを、あれやこれやとかきあつめて売りにだし、どうにか、かじか沢を売らずにすませました。
もはや、家にのこっているものといったら、なんのねうちもないような、絵のかいてない白いびょうぶぐらいのものでした。
その晩のこと、菊三郎はゆめの中で、なんだかおそろしくたくさんのかじかの声を聞いたような気がしました。
このあいだ山で聞いたときとはちがって、それはたのしそうな声でした。
目がさめると、もうあたりはあかるくなっています。
菊三郎は、ふとんの中でのびをすると、
「ありゃっ?」
のばした手が、つめたいものにさわりました。
おどろいておきあがってみると、なんと、まくらもとがビッショリとぬれています。
そればかりか、水にぬれた小さな足あとが、縁側のほうからつづいているではありませんか。
その足あとの先を見ておどろきました。
「あっ!」
なんと目の前のびょうぶには、いつのまにか墨の色もあざやかに、たくさんのかじかがえがかれているではありませんか。
そのびょうぶは、見れば見るほどよくかけています。
とんだりはねたり、のどをふくらましたりと、本物そっくりです。
どんな名人がかいたかしりませんが、ほんとうに、いまにも鳴きだしそうでした。
さて、菊三郎のかじかびょうぶは、あっというまにひょうばんになって、村じゅうはもちろん、遠い町々からも見物がくるようになりました。
しまいには、都の名高い絵師たちまでが、わざわざ見にきて、おどろきかんしんしてかえるのです。
千両箱をいくつもかさねて、ゆずってくれといってくる人も、ひとりやふたりではありませんでしたが、菊三郎はどうしても、このびょうぶを手ばなす気にはなりませんでした。
そして、なまけものだった菊三郎が、まるで人がかわったように、はたらきだしたのです。
おかげで、だんだん田畑もふえて、むかしにまけないほどのりっぱな家になりました。
人がらも、むかしの菊三郎とは、まるっきりちがいます。
まずしい人には金や米をわけてやり、こまっている人には、ちえをかしてやります。
こうして、菊三郎はしあわせにくらして、もう八十歳をこえる老人になりました。
さすがの菊三郎も、年にはかてません。
からだもガックリとおとろえて、このごろでは、ずっとねたっきりの身となりました。
そんなある日、殿さまの使いの家老(かろう)が、おおぜいの家来をしたがえて、やってきました。
菊三郎のまくらもとに、千両箱をいくつもつみかさねて、天下にひょうばんのかじかびょうぶを売れというのです。
菊三郎は、キッパリとことわりました。
「だいじなびょうぶじゃ、あいてが殿さまであろうと、手ばなすわけにはいかん」
ところが、家老ははらをたてて。
「えい、この無礼者(ぶれいもの)め。殿さまのおぼしめしを、なんとこころえるか。それっ!」
家来どもは、ねている菊三郎をふみこえて、びょうぶをうばってしまったのです。
菊三郎は息もたえだえで、どうすることもできません。
と、そのとき、
ザワザワザワザワ
家老や家来どもの足もとを、何百というかじかが、はってゆくではありませんか。
なんとそれは、家老のかかえている、かじかびょうぶからはいだしてくるのでした。
そして見るまに、かじかびょうぶは、ただの白いびょうぶにかわってしまいました。
「そうじゃ、そうじゃ。それでよいのじゃ。みんな、かじか沢へかえるがよい」
つぶやきながら、菊三郎はニッコリわらって、死んでしまいました。
おしまい
| ジャンルの選択 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 福娘童話集 人気コーナー |
|||||||||||||||||||||||||||
| きょうの新作昔話 未公開の童話・昔話を毎日 一話ずつ公開 |
|||||||||||||||||||||||||||
| おはなし きかせてね 福娘童話集をプロの声優・ナレーターが朗読 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 小学生童話 幼稚園から小学6年生まで、学年別の童話・昔話集 |
|||||||||||||||||||||||||||
| おくすり童話 読むお薬で、病気を吹き飛ばそう! |
|||||||||||||||||||||||||||
福娘の姉妹サイト http://hukumusume.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| 366日への旅 毎日の記念日・誕生花 ・有名人の誕生日と性格判断 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 世界60秒巡り 国旗国歌や世界遺産など、世界の国々の豆知識 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 子どもの病気相談所 病気検索と対応方法、症状から検索するWEB問診 |