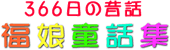| お話しの移動 |
| ・ 福娘童話集 ・ ジャンル別 ・ 日本の悲しい話 (全30話) → 1話 〜 10話 → 11話 〜 20話 → 21話 〜 30話 |
日本の悲しい話 第8話
お花地蔵
むかしむかし、ある村に、おばあさんとまご娘がふたりでくらしておりました。
まご娘の年は七つで、名はお花といいます。
おばあさんの年は六十で、名はお春といいます。
お花の両親は、お花が三さいのときに死んでしまったのです。
お春ばあさんは、よその家の畑しごとをてつだったり、ハリしごとをしたりしてくらしていました。
「ばあちゃ、早くいくぞ」
お花は、お春ばあさんが畑しごとをしているあいだは、子どもたち相手にあそびまわっています。
「えいっ!」
「やあっ!」
男の子たちをやっつけてしまうのは、いつもお花でした。
夕ぐれになると、お春ばあさんとお花は、いっしょに家へ帰りました。
「ばあちゃ、おら、きょう、吾助とごん太をやっつけただ、おもしれかっただ」
「そんなにおもしれかったか。じゃがなあ、お花。棒切れあそびなんて、おなごのするもんじゃあねえ。あれは、男の子のすることじゃあ」
「ばあちゃ、おら、おなごじゃねえ。男の子だ。みとれ」
と、いって、なんと立ったままおしっこをしたのです。
「んま、なんて子じゃ」
やがて、秋になりました。
村はかりいれどきで、ネコの手もかりたいほどのいそがしさです。
お春ばあさんは、あっちの家、こっちの家のてつだいで大いそがし。
でも、お花はあいかわらず、棒切れあそびにむちゅうでした。
「そらこい! どっからでもかかってこい!」
「なにをっ。なまいきな」
「そりゃ、このへっぴりごしめ。どうだ、まいったか!」
「いてっ、いてえよう。お花はつよすぎる」
「あははは」
そうして、夕方になると、畑しごとを終えたお春ばあさんと帰っていくのでした。
家に帰って、お春ばあさんがお花のからだを洗ってやっていると、お花がポツンといいました。
「おら、もう、いくさごっこはやめるだ」
お春ばあさんはおどろきました。
「ど、どうしたんじゃ。なんでやめるんだ? おめえから棒切れとったら、なんにものこらねえでねえか」
「だって、ばあちゃ、おらに勝てる相手が、一人もいなくなっただよ。だから、おら、棒切れあそびをやめて、ばあちゃのてつだいをするだ」
「なにいってるだ。おめえにてつだってもらったって、かえってじゃまになるだけだ。・・・まったく、急になまいきなことをいいよって!」
そういうお春ばあさんのほおに、ポロリとうれしなみだがこぼれました。
ところがその冬、村の子たちが、はやりやまいの『百日ぜき』にかかりました。
「ゴホン、ゴホン、ゴホン」
元気だったお花も、百日ぜきにかかりました。
医者のいない小さな村では、どうすることもできません。
そして、あんなに元気だったお花は、あっけなく死んでしまいました。
お春ばあさんは、とつぜんの悲しみに、何日も何日も、仏だんの前にすわったまま、動こうとしません。
近所の人が、心配してやってきました。
「お春ばあさん、すこしは食べんと、からだにどくじゃで。お春ばあさんにはつらいことじゃが、お花もあの世にいけば、おっとうやおっかあにあえるだ。きっと親子水いらずでくらしてるだよ」
お春ばあさんは、やっと顔をあげて。
「ああ、そのことだけを、おら、いのってただ。・・・じゃがのう、お花はおさねえ。あんなちっちゃいお花が、おっとうとおっかあのところに、まよわずいけるかどうかとおもうと、それが心配でなんねえ」
「だいじょうぶじゃあ、お花はしっかりもんじゃで。きっといけるだよ」
「・・・そうあってくれれば、いいんじゃがのう」
夜になって、またひとりぼっちになると、お春ばあさんは、また仏だんの前にすわりこんでしまいます。
「どこかで、ばあちゃをさがしてるんでねえか。ひとりさびしくないているんでねえか。・・・お花、ばあちゃには、どうしてやることもできねえ。お花は、まるでおじぞうさまのように、 ・・・そうじゃ!」
お春ばあさんは、その夜から、おじぞう(→詳細)さまをほりはじめました。
おさなくして死んだお花は、ごくらくへの道もわからずまよっているかもしれません。
そこでお春ばあさんは、おじぞうさまをつくって、たくさんの村の人たちにいのってもらい、早くお花をごくらくへ送ってやろうと思ったのです。
お春ばあさんは、くる日もくる日も、おじぞうさまをほりつづけました。
「でけた!」
こうして、長い冬がすぎて、あたたかい春がくるころ、おじぞうさまはできあがりました。
お花にそっくりの、小さな小さなおじぞうさまです。
「これできっと、おっとうとおっかあにあえるにちがいない」
お春ばあさんはそう思いました。
そして、その小さなおじぞうさまは、村を見わたせるおかの上にたてられました。
このおじぞうさまは、やがて『お花じぞう』とよばれるようになり、子どもが百日ぜきにかかると、お花のすきだった「いり米」をおそなえしておねがいすれば、かならずよくなるといわれるようになりました。
おしまい
| ジャンルの選択 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 福娘童話集 人気コーナー |
|||||||||||||||||||||||||||
| きょうの新作昔話 未公開の童話・昔話を毎日 一話ずつ公開 |
|||||||||||||||||||||||||||
| おはなし きかせてね 福娘童話集をプロの声優・ナレーターが朗読 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 小学生童話 幼稚園から小学6年生まで、学年別の童話・昔話集 |
|||||||||||||||||||||||||||
| おくすり童話 読むお薬で、病気を吹き飛ばそう! |
|||||||||||||||||||||||||||
福娘の姉妹サイト http://hukumusume.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| 366日への旅 毎日の記念日・誕生花 ・有名人の誕生日と性格判断 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 世界60秒巡り 国旗国歌や世界遺産など、世界の国々の豆知識 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 子どもの病気相談所 病気検索と対応方法、症状から検索するWEB問診 |