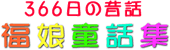| お話しの移動 |
| ・ 福娘童話集 ・ ジャンル別 ・ 百物語の朗読 ・ 日本のこわい話(百物語) → 1話 〜 10話 → 11話 〜 20話 → 21話 〜 30話 → 31話 〜 40話 → 41話 〜 50話 → 51話 〜 60話 → 61話 〜 70話 → 71話 〜 80話 → 81話 〜 90話 → 91話 〜 100話 |
| - 広 告 - |
百物語 第七十八話
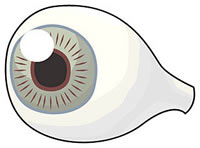
目玉だらけ
東京都の民話
むかしむかし、江戸のある町に多吉(たきち)という、若いたたみ職人がいました。
多吉は大変な働き者で、朝早く家を出て夜おそくまで、親方のところでいっしょうけんめいたたみをつくっていました。
ある日の事、夜ふけ近くまで働いた多吉は、親方のところでお酒をふるまわれて、ほろよいきげんで長屋(ながや→今で言う、アパート)へかえっていきました。
♪春じゃ、春
♪月もおぼろの
♪なんとやら
多吉はいい気分でうたいながら、町はずれの橋のところまで歩いてきました。
すると橋のたもとのやなぎの木の下に、子どもをだいた女の人がジッと川を見つめて立っていました。
(おおっ、こいつはいい女じゃ。しかしいまごろ、こんなところでなにをしているんだ? ・・・おい、まさか、身なげしようというんではあるまいな)
足をとめてのぞきこむと、女の人はふりむいて多吉に声をかけてきました。
「すみません。ちょっと、お手をかしていただけませんか。子どものたびがぬげそうなので、なおしていただきたいのです」
顔も美しければ、声も美しい、ほれぼれとするような若い女の人です。
「それぐらい、おやすいご用です。ほほう、かわいいお子さんだ」
子どもの顔はお酒をのんだようにまっ赤で、目もつりあがり、みけんに三本のたてじわがあります。
正直に言うと、ちっともかわいくないのですが、多吉はおせじをいって子どものたびをなおそうとしました。
そしてきもののすそをまくりあげると、なんと子どもの足は毛むくじゃらで、毛のなかにはカエルのタマゴみたいな小さな目玉が、うじゃうじゃとあったのです。
そしてその目玉が、一度に多吉の事をにらみました。
「うぎゃー! でたぁー!」
多吉はビックリしてのけぞると、わき目もふらずに逃げ出しました。
橋をわたってダンゴ屋のかどをまがり、地蔵さんの前を走りぬけて、やっとお寺の前まできて、
「ふうーっ」
と、大きなため息をつきました。
ちょうどお寺の前に知りあいの和尚(おしょう)さんがたっていたので、多吉は今見たバケモノの話しをしました。
「ああっ、和尚さんがいて助かりました。実はいま、あそこの橋のたもとのやなぎの木の下で、目玉ばかりのバケモノにであったのです」
多吉の話しをきいていた和尚さんは、カラカラと笑いながら、
「それは大変じゃったな。して、そのバケモノはこんなバケモノじゃ、なかったですかな?」
そういっていきなり、ころものすそをまくりあげました。
和尚さんの毛むくじゃらの足とおしりは、小さな目玉だらけだったのです。
その目玉が多吉の顔をみて、ニヤリと笑い出しました。
「うーん!」
あまりの事に、多吉はうなり声をあげると、そのまま後ろにひっくりかえって気絶してしまったという事です。
おしまい
| ジャンルの選択 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 福娘童話集 人気コーナー |
|||||||||||||||||||||||||||
| きょうの新作昔話 未公開の童話・昔話を毎日 一話ずつ公開 |
|||||||||||||||||||||||||||
| おはなし きかせてね 福娘童話集をプロの声優・ナレーターが朗読 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 小学生童話 幼稚園から小学6年生まで、学年別の童話・昔話集 |
|||||||||||||||||||||||||||
| おくすり童話 読むお薬で、病気を吹き飛ばそう! |
|||||||||||||||||||||||||||
福娘の姉妹サイト http://hukumusume.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| 366日への旅 毎日の記念日・誕生花 ・有名人の誕生日と性格判断 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 世界60秒巡り 国旗国歌や世界遺産など、世界の国々の豆知識 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 子どもの病気相談所 病気検索と対応方法、症状から検索するWEB問診 |