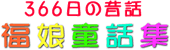| お話しの移動 |
| ・ 福娘童話集 ・ ジャンル別 ・ 日本の悲しい話 (全30話) → 1話 〜 10話 → 11話 〜 20話 → 21話 〜 30話 |
日本の悲しい話 第6話
オオカミばあさん
京都府の民話
むかしむかし、丹波(たんば→京都府)の山間の村に、スギというおばあさんがすんでいました。
ある年、おスギおばあさんに、待望の孫が生まれたのです。
「ああ、うちにも孫がでけた。ええ男の子や。ほんに、ええ男の子や」
ですが、そう言って喜んでいたのもつかの間で、その年の秋、息子夫婦と可愛い孫が、流行病で死んでしまったのです。
一人生き残ったおばあさんは、生きる気力を無くしてしまい、
「たった一人、生きていてもしかたねえ、はよう、わしも死なしてくれえ」
と、ただ泣いてくらしていました。
まもなく冬がきて、山に雪が降り始めた頃、おそろしいオオカミが里の方へおりてきました。
そして里の子どもがオオカミに食い殺されたので、村人たちは大騒ぎです。
おスギおばあさんが人前に姿を見せなくなったのは、その頃からでした。
と、いっても、決していなくなったわけではなく、夜になると家には明かりがつきましたし、かまどの煙もあがります。
そのころ、村には恐ろしいうわさが広がりました。
「なあ、知っとるか? あのばあさん、オオカミを飼っとるんや」
「ああ、聞いた聞いた。何でも朝晩、オオカミにめしを食べさせているそうだ」
うわさはうそではないらしく、夜ごとに、
「ウォーン! ウォーン!」
と、いう、オオカミの鳴き声がすぐ近くで聞こえ、月明かりの庭先を通っていく黒いけものを何人もの村人が見たのです。
そこである晩、男たちが火なわ銃を持って、おスギおばあさんの家の近くへ行ってみました。
ひっそりとした、おスギおばあさんの家には、あんどんの明かりが灯っていました。
その明かりで、しょうじに大きくおばあさんとオオカミの影が写ったのです。
「あわわわわ、オオカミ、オオカミだ!」
鉄砲を持った男たちは、みな足がすくんでしまい、
「あんなのに飛びかかられては、このくらい夜のこと、いくら鉄砲があっても殺されてしまうぞ」
と、ぞろぞろ逃げて帰りました。
それからしばらくしたある日、おスギおばあさんは珍しく外へ出かけると、お坊さんを連れて戻って来ました。
お坊さんは土間(どま→台所)から飛び出してきたオオカミを見てビックリしましたが、そのオオカミに向かって、おばあさんがいいました。
「わしなあ、お前が家の裏まできた日には、『はよう、わしを食べてくれ、息子や孫のところへ行かしてくれ』そう思うて戸を開けたんや。そやけどお前は、このわしを食べなんだ。それどころか、わしが炊いたごはんをうまそうに食べて、今までいてくれた。おかげで、わしは今日まで命をながらえることができた。お前には礼をいわんならん。だども、いつまでもというわけにはいかん。ありがたいお経を聞いて、山の仲間の所へ帰ってくれ。・・・では、お坊さま、頼んます」
「あっ、・・・えっ、おほん。それならオオカミや、よう聞くがええ」
お坊さんは、あがりがまち(→家のあがり口)に立って、お経をとなえだしました。
オオカミはキバをむいて土間を歩きまわっていましたが、しだいに落ち着いて、お坊さんの前に座り込みました。
オオカミは、そばにいたおばあさんをチラリと見ると、眠ったように目をつむります。
それを見たおばあさんは、ゆっくりと部屋を出て行きました。
しばらくの間、お坊さんのお経が続いていましたが、突然、
ズドーーン!
耳をつんざく音が、後ろの山の方までこだましたのです。
しょうじのかげには、鉄砲を構えたおばあさんが立っていました。
お経を聞いていたオオカミは、血に染まって死んでいました。
おばあさんの目から、涙があふれておちました。
「なんぼわけがあるいうても、お前は村の子どもや旅の人を襲うた。つらいけど、わしはこうするしかなかったんや。ごめんな。ほんまに、ごめんな」
そしてお坊さんの手を借りて、オオカミのなきがらを山へ運ぶと、手厚くほうむりました。
それからは、村ではだれ一人オオカミに襲われる者はなかったそうですが、おスギおばあさんはその日から姿を消して、二度と村には戻ってこなかったという事です。
おしまい
| ジャンルの選択 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 福娘童話集 人気コーナー |
|||||||||||||||||||||||||||
| きょうの新作昔話 未公開の童話・昔話を毎日 一話ずつ公開 |
|||||||||||||||||||||||||||
| おはなし きかせてね 福娘童話集をプロの声優・ナレーターが朗読 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 小学生童話 幼稚園から小学6年生まで、学年別の童話・昔話集 |
|||||||||||||||||||||||||||
| おくすり童話 読むお薬で、病気を吹き飛ばそう! |
|||||||||||||||||||||||||||
福娘の姉妹サイト http://hukumusume.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| 366日への旅 毎日の記念日・誕生花 ・有名人の誕生日と性格判断 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 世界60秒巡り 国旗国歌や世界遺産など、世界の国々の豆知識 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 子どもの病気相談所 病気検索と対応方法、症状から検索するWEB問診 |