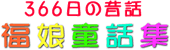| お話しの移動 |
| ・ 福娘童話集 ・ ジャンル別 ・ 百物語の朗読 ・ 日本のこわい話(百物語) → 1話 〜 10話 → 11話 〜 20話 → 21話 〜 30話 → 31話 〜 40話 → 41話 〜 50話 → 51話 〜 60話 → 61話 〜 70話 → 71話 〜 80話 → 81話 〜 90話 → 91話 〜 100話 |
| - 広 告 - |
百物語 第十六話

雪のなかの女ゆうれい
新潟県の民話
むかしむかし、雪のふかい魚沼(うおぬま)の里に、源教(げんきょう)という坊さんがいました。
ある冬、熱心に寒行(かんぎょう→寒さをしのんでする修行)をつとめて、その行も最後の夜となり、魚野川(うおのがわ)にかかる橋のたもとへでかけました。
このあたりでは橋の上にも大雪がつもるため、わたるときに足をすべらせて、川へおちる人が少なくなかったのです。
坊さんが鐘(かね)をたたきながら念仏をとなえていると、にわかに月の光がくらくなりました。
そして川の中から、フワフワと青い火がもえあがってきたのです。
(これはきっと、水死した人たちのたましいの火だ)
坊さんは目をとじて念仏の声をあげ、しばらくしてから目をあけました。
すると橋の上に、年のころは三十くらいの女が立っていました。
青ざめた白っぽい顔で、髪の毛がぐっしょりとぬれています。
まるでたったいま、水からあがってきたかのようです。
それによく見ますと、からだが半分すきとおっていて、足元は完全に見えません。
(これこそ、ゆうれい)
坊さんがなおも念仏をとなえますと、女はスーッと近づいてきて、よわよわしい声でいいました。
「わたしは、山むこうの里のキクともうすもの。夫にも子どもにも死なれ、くらしがたたなくなったので、このさきの親類(しんるい)をたよろうと、ここまで来たのですが、橋をわたるときに足がすべって川へ落ちて水死したのです。今夜が四十九日になりますが、だれ一人、わたしに気づいてくれませんでした。そんな時、お坊さまが念仏をとなえてくれて、どれほどありがたかったことか。ああ、これで極楽(ごくらく→天国)へいけると。・・・だけど、わたしのこの黒髪がじゃまになって、極楽へまいることができません。お坊さま、どうかわたしの毛をそってください」
いいおわると、女はさめざめと泣くのでした。
そこで、坊さんが、
「そのくらいはたやすいこと。すぐにも黒髪をそってしんぜたいが、今は、かみそり一つ持っていない。あすの夜、わしが住む関山(せきやま)のいおり(そまつで小さな家)へ、おいでなされ」
と、言うと、女はけむりのように消えて、また月が明るくなりました。
次の日、坊さんはふと考えました。
(ゆうれいの女は、きっとやってくるだろう。わしが黒髪をそっても、だれかが証人(しょうにん)として見ていてくれなければ、だれも信じてはくれまい。この村の七兵衛(しちべえ)は一緒に念仏をとなえる男だから、あれにたのむとしよう)
坊さんはさっそく七兵衛を呼んで戸だなにもぐりこませると、すき間から部屋のようすが見えるようにしました。
さてその夜、坊さんがいろり(→部屋のゆかを四角く切り、たきぎなどをたくようにした所)にあたりながらジッと待っていると、いつ入ってきたのか、キクという女が仏壇(ぶつだん)にむかってすわっていました。
さすがの坊さんも、ビックリしましたが、
「キクどの、よくおいでなさった」
と、声をかけました。
しかし女は頭をたれているだけで、今夜は何も言いません。
坊さんがかみそりを手にとると、ぬれた女の黒髪を切り落としました。
(この髪をとっておいて、そったあかしとしよう)
坊さんが切り落とした髪の毛を自分のふところへしまおうとすると、不思議なことに、髪の毛は糸でひっぱられるように女のふところへ入ってしまうのです。
坊さんがいくら髪の毛をしっかりにぎりしめても、髪の毛はスルリスルリと女のふところへ入るため、全ての髪の毛をそりおえた時には、坊さんの手にほんのかぞえるほどの髪がのこっているだけでした。
(ありがとうございました。では、これで)
女は小さな声で礼を言うと、スーッときえてしまいました。
「ああ、なんとおそろしいものを見たことか」
戸だなから出てきた七兵衛は、ブルブルとふるえていました。
そして七兵衛は出家(しゅっけ→家を出て仏門に入ること)をして、坊さんになりました。
源教(げんきょう)の手にのこったゆうれいの髪は、関山(せきやま)に塚(つか)をたてておさめ、毛塚(けづか)とよんで今ものこっているという事です。
おしまい
| ジャンルの選択 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 福娘童話集 人気コーナー |
|||||||||||||||||||||||||||
| きょうの新作昔話 未公開の童話・昔話を毎日 一話ずつ公開 |
|||||||||||||||||||||||||||
| おはなし きかせてね 福娘童話集をプロの声優・ナレーターが朗読 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 小学生童話 幼稚園から小学6年生まで、学年別の童話・昔話集 |
|||||||||||||||||||||||||||
| おくすり童話 読むお薬で、病気を吹き飛ばそう! |
|||||||||||||||||||||||||||
福娘の姉妹サイト http://hukumusume.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| 366日への旅 毎日の記念日・誕生花 ・有名人の誕生日と性格判断 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 世界60秒巡り 国旗国歌や世界遺産など、世界の国々の豆知識 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 子どもの病気相談所 病気検索と対応方法、症状から検索するWEB問診 |