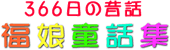福娘童話集 > 日本昔話 > 読者からの投稿作品 >海をわたる蝶
第 35話
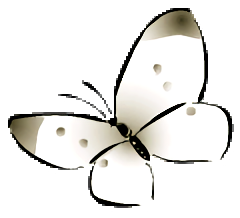
※本作品は、読者からの投稿作品です。 投稿希望は、メールをお送りください。→連絡先
投稿者 「天乃悠の朗読アート」 天乃悠の朗読アート
海をわたる蝶
投稿作品
すきとおるほど真っ白な
一羽のチョウ
草花の中でうたい おどった
ある日 突然
木の葉のあいだから 奇妙な色の光がさした
天から告げられた 命の運命(さだめ)
チョウはまっすぐ光にむかい翔びたった
そして ながい 年月がすぎた
あわい色の花びらが舞うなか
ふと足もとに 一羽のチョウが
ひっそりと息たえようとしている
どれほどの間 翔びつづけたのか
なぜこれほど 傷ついたのか
永遠の眠りについたとき
チョウは美しくその姿をかえ
ふたつをむすぶ 大きな 結い目となった
二〇〇二年。サッカーワールドカップが、日本と韓国、二つの国で開かれました。
世界中からたくさんの人々が訪れ、満員のスタジアムには各国の国旗やペナントが力強く風にゆれ、大歓声がうずまいていました。
そこに、同じように飾られることを望んで手作りをされたペナントがありました。
ペナントは、日本と韓国の国旗の間に、チョウが舞いおりたように美しいリボンをあしらったものでした。
ペナントを作ったのは、金寿姫さん。八十歳を越えた韓国のおばあちゃまです。
ペナントは各国の代表に配られましたが、そのことは人々に広く知られることはなく、ワールドカップは終わりました。
ベナントには、金寿姙さんの深い想いが込められていました。
それは、平成元年。
一九八九年四月、韓国の地でひっそりと亡くなられた李方子さまへの想いだったのです。
李方子さまは、明治三十四年、日本の皇族梨本宮家の第一王女として生まれました。
梨本宮方子さまが、のちの李王朝「大韓帝国」最後の皇太子、李銀殿下のお妃となり李方子さまとなるのです。
今の韓国と北朝鮮は、その昔「大韓帝国」という一つの国でした。
半島すべてをおさめていた李王朝最後の皇太子が垠殿下なのです。
そして日露戦争ののち、大韓帝国は日本の保護国となり、さらにそののち併合され、垠殿下は日本の皇族と同じ教育をうけるため、日本に留学することになりました。
それは当時、韓国統監であった伊藤博文がまだ幼かった垠殿下にはじめて会った時、「この方は良い教育をうければ必ず立派な君主になられる方だ」と感じたからでした。
垠殿下は東京の学習院に入学し、まさに日本の皇族に準じる存在の王族となっていきました。
一方、方子さまは幼いころから、お琴にピアノ、フランス語に和歌など、皇族としての教育を受けながら、忙しい毎日をすごしていました。
春になれば庭でつくしをつんだり、秋には紅葉山の絵を描いたりと、おだやかな日々もありました。
しかし大正時代になり、方子さまの運命は大きく変わっていきます。
方子さまが十五歳の夏。大磯という海岸の近くにあった別荘で、母と娘三人、楽しくすごしていました。
ほのかに潮の香りがただよう、静かな朝のことでした。
方子さまは新聞を広げて、
「これは……」
と息をのみました。韓国の皇太子、李垠殿下の婚約発表の記事が大きくのっていたのです。
その垠殿下の横に、お嫁さんとしてならんでいるのが、なんと自分の写真だったのです。
「韓国の王子さまと結婚?」
新聞を手にしている方子さまの手はふるえ、激しく立ち上がりました。
「いったいなぜわたくしが」
するとそこへ、方子さまのお母さまが入ってきました。
「どんなにか驚いたことと思います。実は大臣がたびたびお見えになって、ぜひ方子を殿下のご結婚相手にと、お話があったのです。
――このお話は、日本と韓国がよりいっそう仲良くなり、
力を合わせるようにと考えられた国と国との結婚です。
一つとなった両国が力をつけなければ、いつ大きな国に飲み込まれ、やがてはわたしたちの国はなくなってしまうかもしれない。
―-そのようにそのようにおっしゃるのです。
大臣は方子に、韓国と日本を救ってくれと言われたのですよ。
お父さまとも何度もご相談をいたしました。
これは大きな役割りですからお断りしようと、お父さまもわたくしも、ずいぶん考えたのですが……」
お母さまは、目に涙をいっぱいにためて、苦しそうに話したのです。
その顔を見て、方子さまは胸をえぐられるような思いがしました。
“お母さまは今、わたしにわびておられる。わたしの知らないところで、お父さまとお母さまが苦しんでこられた”
とお二人の気持ちが伝わってきたのです。
それから二人、だまったまましばらく波の音を聞いていました。
方子さまは、くり返し打ち寄せるおだやかな音を聞くたびに、
"わたしが心を決めるしかないのだ"
少しずつ、にぎりしめていた手の平に力を込めました。
やがて、
「わかりました。この結婚によって日本と韓国の王室が固く結ばれれば、必ず両国民のためになるのですよね」
お母さまは驚いたように顔を上げ、方子さまの目をじっと見つめました。
「そうですね。かけ橋の一つになり、両国民の模範とならなくてはいけまん」
「それが人々のためになるなら、喜んでまいりましょう」
方子さまは、窓の外に広がる海を見ながら、きっぱりと言いました。
「ありがとう……よく言ってくれましたね……」
方子さまの肩を強く抱き、お母さまは声を上げて泣きました。
垠殿下は、十一歳のときから日本で暮らしていました。
それは、日本の皇族と同じ教育を受けるためでした。
韓国の王室で暮らす家族と離れ、垠殿下は立派な青年に成長していきました。
方子さまが垠殿下に初めて会った日。
「国王としてたった一人でも、この背中にすべての人々の未来を背負って歩いてゆかなければなりません。私は子供のころから、自分に言い聞かせてまいりました」
方子さまは静かにうなずきながら、
「故郷を離れてどんなにお寂しいことでしたでしょうに。なんとご立派な……”
心の中でつぶやきました。
それから二人で、日曜日ごとにお庭の散歩をしたり、時にはトランプをして楽しいひとときをすごしていきました。
ほとんど言葉をかわすこともなく、短い時間をただお茶を飲んですごしたときもありました。
垠殿下は、突然の結婚を言いわたされた方子さまを気づかい、とても優しくしてくれました。
やがて
"この方とならいっしょに歩いてゆける"
方子さまも垠殿下も、お互いを思う気持ちをしっかりと育て、結婚することになりました。
大正九年四月二十八日。
木々の緑が輝き、すっきりと晴れたすがすがしい朝でした。
二頭だての馬車が方子さまを迎えに来ています。
「お父さま、お母さま……」
方子さまは別れのあいさつをしようとしますが、涙があふれ、なかなか言葉になりません。
「苦しいことも多いでしょうが、どうか立派な妃殿下に……」
目をうるませるお母さまの横に、深くうなずいているお父さまがいます。
「ありがとうございました」
突き上げてくる思いを胸に、ようやく短いあいさつをかわした方子さまは、馬車に乗り込みました。
馬車は御殿へ向かって走り始めました。
御殿には、皇族を代表する方々がたくさん集まっていました。
方子さまはローブデコルテ。まっ白な絹地に刺繍を施されたドレスです。
垠殿下は、昇進したばかりの陸軍中尉の礼服姿でした。
皇族の儀式のならわし、十二単ではなく、国を超えた特別な例として準備された衣装で結婚式はとりおこなわれました。
すべてが終わったとき、垠殿下は言いました。
「疲れたでしょう。ゆっくりおやすみなさい。これからは、わたしがそばにいますからね」
「いいえ、疲れてなどおりません。ようやく殿下のお心にたどり着けたようで、なんと安らかな気持ちでしょう。これからどのようなことがあっても殿下のおそばでせいいっぱい生き、殿下をお守りし、殿下のおそばで死のうと思います」
方子さまは殿下に誓いました。
こうして方子さまは韓国の李方子妃殿下として生きていくことになったのです。
時代は大正から昭和へと移り変わっていきます。
昭和に入ると、日本も世界も激しくゆれ動き始めます。
昭和十六年、第二次世界大戦が始まってしまい、資源のとぼしい小国日本は負けてしまいました。
方子さまと垠殿下の運命はこの戦争によって大きく変わっていくのです。
垠殿下と方子さまは、敗戦によって「臣籍降下」の命を下され、韓国の王族でも日本の皇族でもなくなっていきます。
敗戦で傷ついた日本の町中に、突然一般の国民として放り出されてしまいました。
韓国では李王家も滅び、新しい大統領が生まれました。
しかし、この大統領は二人が韓国へ帰ることを許しませんでした。
李王朝の血を受け継ぐ垠殿下が帰ってくると、自分の地位や立場があやうくなると考えた人たちがいたからです。
それは、垠殿下にとって本当につらいことでした。
「わたしは、日本人でも韓国人でもなくなってしまった。わたしは、どこまでもおし流されていくしかないのか」
寂しそうな殿下の様子を見て、方子さまは何度涙を流したことでしょう。
幼いころに国を離れた垠殿下に、せめて残りの人生は故郷の風や雲と語り合い、花や鳥にいたわられ、人々の優しさにふれていただきたいと考えていたからです。
「この激しい流れを渡りきり、かならず故郷へたどり着きましょう」
方子さまは殿下に力強く語りかけました。
売り払われた二人のお屋敷。方子さまは門のそばで、庭に残った梅の木や色とりどりの花々をながめていました。
そのひとつひとつに昔の香りがしてきます。
ふと、サツキの花を見て語りかけました。
「この花々や庭の木がもしも口をきけたなら、いつか私と昔の思い出話しをしてくれないかしら」
そして、残されたクリーム色のカーテンを静かにはずし持ち帰りました。
それを、一針一針思いを込めて布団やブラウスに縫いかえてゆきます。
あれはてた町中で、お金の使い方もわからなかった二人ですが、東京の田園調布という町で、つつましく幸せな家庭を築き始めていたのです。
着物はすべて手放し、お米や野菜を買いました。
温かい料理を作り、韓国の着物を着て殿下の帰りを待ちました。
「これからは、私が強くならなくては」
故郷へ帰ることすらできなくなった殿下の心の痛みをやわらげることが、何よりも方子さまの願いでした。
こうして二人は、皇太子でも妃殿下でもなく、日本で暮らす韓国人の夫婦として小さな家庭をひっそりと数十年も守っていきました。
昭和三十八年、韓国の大統領が変わりました。
新しい大統領は、人々の心をいたわることのできるとても優しい人でした。
垠殿下の気持ちを考えて、なんとか韓国へ帰ることができるよう手厚くとりはからってくれたのです。
ところがこの時すでに垠殿下は、脳軟化症という重い病を背負い、ほとんど意識はありませんでした。
韓国へ帰る日。
ベッドに横になったままの垠殿下とともに方子さまは空港へ向かいました。
お二人を故郷へ送るためだけに用意された飛行機が待っています。
「殿下、ようやく故郷に帰ることができますね。あちらへ着いたら、すぐに病院へおつれくださるそうです。またいつかと同じように、日本と韓国は力を合わせてくれたのですよ」
もちろん殿下に返事はありません。
方子さまは、飛行機の窓からだんだんと小さくなっていく日本の景色を見ながら、
「さようなら、わたしの故郷」
今までどんなにつらくても、涙を見せずがんばってきた方子さまですが、この日だけは、意識のない殿下のそばで声を上げて泣きました。
そしてようやく、方子さまは六十二歳、垠殿下は六十六歳、韓国で暮らすことができるようになりました。
方子さまの新しい暮らしは、垠殿下の看病と障害者福士のために力をそそがれました。
それは、そのころの韓国は、まだまだ障害のある人々に対しての理解を深める必要があるとお考えになったのです。
そこで、こうした人々のための職業訓練所を作り、さらに、子どもたちの教育のため、学校を作ることを考えました。
そのためには、とてもたくさんの資金が必要です。
しかし、王公族を離れて一般の韓国人として生きる方子さまにはそんな大金はありませんでした。
それでも方子さまは、自分が描いた絵や、焼き物、書などを売って、けんめいにお金を作りはじめました。
手が大きくはれ上がっても、求めてくださる方があれば、何枚も絵を描き、書を書きつづけました。
すると、韓国の子供たちのために尽くされている方子さまを、「なんとか助けたい」「資金を出しましょう」と、日本の経済界から何人かの人が名乗りを上げました。
韓国でも、資金集めに走り回ってくれたり、建物を貸してくれたりする人もあらわれました。
いつしか方子さまの真心が、大きく人の心を動かしていったのです。
昭和四十二年十月二十日。
垠殿下のお誕生日に合わせ、韓国に初めての障害者福祉施設が誕生しました。
倉庫の片隅を借りた小さな施設は、「明暉園(めいきえん)」と名づけられました。
方子さまは、知的障害者のための学校を新たにつくりたいという思いから、ある「ろうあ学校」の見学をすることにしました。
そこで当時、韓国語がまだ片言しか話せなかった方子さまのために、通訳としてその日呼ばれた女性が金寿姙(キムスイム)さんでした。
金寿姙さんは、大正10(1921)年、日本の統治下であった開城(ケソン・現在の北朝鮮)という町のとても裕福な家庭に生まれました。
韓国語と日本語、両方の言葉で高い教育を受けながら少女時代をのびのびと育ち、19歳で同じ町の人と結婚をしました。
その後満州へわたり男の子を授かりました。
幸せな結婚生活をおくっておりましたが、男の子が生後半年で髄膜炎という病気になってしまい聴覚に障害をおってしまいました。
金寿姙さんは重い障害をもった我が子に、できる限りの教育を受けさせてやりたいと願い、終戦後韓国へ引きあげ、息子をろうあ学校へ入学させました。
金寿姙さんの息子は、お母さんとともに人の何倍も努力をして、ろうあ学校を立派に卒業して教師になりました。
方子さまがろうあ学校を見学していた日、子供たちと同じように、耳も聞こえず話すこともできない一人の教師がいました。
先生を見つめる子供たちの目はいきいきと輝き、ただひたむきに先生を見つめています。
障害とたたかっている子供たちを見る先生も、そのすべてを受けとめているように温かいのです。
心の通い合うすばらしい授業でした。
重い障害を乗り越え、教師を務めていたのが金寿姙さんの息子でした。
「金寿妊さん、どうかあなたの力を貸していただけないでしょうか」
心を打たれた方子さまは声をかけました。
金寿妊さんは、方子さまが差し伸べた手のぬくもりにはかりしれない優しさと気高さを感じていました。
そして、手を取りき、自然に涙があふれ出していました。
金寿妊さんは、その日から方子さまのそばでお手伝いをすることになりました。
施設はすべてが手作りで、金さんの小さな奉仕室にはまだ、イス一つおいていないところからの始まりです。
壁紙をはり、ミシンを運び、カーテンを作りました。
冷蔵庫を入れ、電話を引きました。
方子さまが用意した布や針で、ショールやマフラーを編み、カーテンや着物を作った残りの布で、小さな袋を作りました。
そして、方子さまの絵や焼き物と同じように、金さんの手から生まれた品々は、つぎつぎと売れ、何もなかった小さな奉仕室にたくさんの希望があふれていきました。
ところがそんなとき、ろうあ学校で教師をしていた息子が、転倒して頭を強く打つ事故がおきてしまいます。
開頭手術をうけたのですが、ついに脳にも障害を起こしてしまいました。
耳の障害を乗り越えて教壇にたっていた息子は、全身麻痺で寝たきりになってしまいました。
金さんは天を見上げ、つぶやきました。
「神さま、この子がいったいどんな悪いことをしたというのですか」
お医者さまや、まわりの人たちに相談をしても、
「安楽死を考えたほうがいいのでは……」
答えはとても残酷でした。
「私の息子は、もうだめかもしれません」
金さんは、方子さまにすがるように言いました。すると方子さまは、
「何を言っているの!母親ならばどんなときも希望を持つのです。信じていれば、きっと奇跡だって起こるはず。奇跡はあなたが起こすのですよ」
方子さまの声は、金さんの背中をなでながらふるえていました。
故郷へ帰って六年と六か月。寝たきりの垠殿下を思いうかべながら、方子さまは自分に言い聞かせていたのです。
金さんはそのとき、方子さまのひざで子供のように泣きました。
昭和四十五年五月一日。
けんめいに垠殿下のお世話をつづけてきた方子さまに、いちばん恐れていた時が訪れてしまいます。
垠殿下と方子さまの金婚式から四日後のことでした。
殿下は、全身に麻痺が起こったまま意識を失ってしまったのです。
「殿下、どうか目をお開けください。ご自分の足で、どうか一歩でも故郷の土を踏んでみてください」
しかし、方子さまの声は届きませんでした。
垠殿下、七十三歳葉桜の候、ついに遠く旅立ってしまいました。
おそうしきの日。
まっ白な李王朝の喪服姿で、ひつぎに寄り添う方子さまを見て、韓国の人々は目を見はりました。
「あのお方は、すっかり韓国李王朝、垠殿下の妻になられましたね」
「なんとご立派な妃殿下でしょう」
今まで韓国の子供たちのために、どんなに走り回っても、
「よその国で今さら何を!」
と、ののしられ、韓国の子どもたちを思って障害児施設を建てたときも、
「日本人がよけいなことを!」
と、なかなか認めてもらえなかった方子さまが、このとき初めて韓国の人たちに方子妃殿下として心から受け入れられたのでした。
そしてそのころ、金寿姙さんもまるで生まれかわったようでした。
方子さまの言葉を胸に、奉仕の仕事に生涯をささげ、方子さまをそばで支えることを誓いました。
訓練所では、ミシンや編み物、木彫りなど、金さんは、子供たちの手を取り、ていねいに教えていきます。
学校はしだいに生徒が増え、大きくなっていきました。
方子さまや金さんの努力が実り始めたのです。
そして昭和四十六年、第二の施設「慈恵学校」が開設されました。
ある日、奇跡は本当に起こりました。
金さんが、居間でお茶を飲んでいたときです。
「カチャ」と居間の扉が開く音がしました。
「お……かあ……さ……ん」
かすかに声が聞こえます。
振り向くと、寝たきりだった息子がベッドから起きあがり歩いているのです。
金さんをみて、ほほえんでいるのです。
金さんは驚いて声も出ず、立ち上がることもできません。
すると息子は、扉のそばに落ちていた百ウォン札を拾い、金さんの上着のポケットにそっと入れてくれたのでした。
金さんは泣きながら、信じられないというような表情で息子の顔を何度も見ては抱きしめました。
そしてほめてやりました。
「おまえは、お金を自分のポケットに入れるのではなく、わたしのポケットに入れてくれるのよね。ありがとう」
「神さま、方子さま、本当に奇跡が起きました。この子が、奇跡を起こしてくれました。」
少しでも望みをなくし、下を向いていたことを、恥ずかしいと思いながら、方子さまの言葉を思い出していました。
次の日、うれしそうに話す金さんの手を握り、方子さまは言いました。
「そう! よかった! よかったわね。金さん、あなたのこの手です。心のこもったこの手が奇跡を起こしたのですよ。人に尽くすということは、言葉やお金ではなく、この手で、温かい手でするものですよね」
この出来事は、金寿妊さんの人生で決して忘れることのできない、大切な宝物となりました。
こうして、日本と韓国のかけ橋になると誓った李方子さまも、そばで方子さまを二十五年間支えつづけた金寿姙さんも、二人が歩んだ道は、決しておだやかではありませんでした。
方子さまは、明治、大正、昭和と、日本が激しくゆれ動いた時代を力いっぱい羽ばたきました。
そして、その時代が終わりをつげた平成元年、ひっそりと幕を下ろすように亡くなりました。
その愛が、韓国の人々の心に生きつづけ、いつしか障害者たちの母と言われるようになったのです。
帰国して、故郷の地を元気に歩くこともなく亡くなった垠殿下とともに、今は、小高い丘の上で韓国の土となり、静かに眠っています。
方子さまが亡くなって十四年。
金寿姫さんは、方子さまの好きだったお料理を作り、月に二度のお墓参りを、欠かしたことがありません。
雨がふっても、強い風にあおられても、小さな身体でけわしい山道を登っていきました。
「こんなお天気なのに、ごくろうさま」
門の近くで、いつも鳴いているカササギを見上げ、たのもしい門番にあいさつをして通りすぎます。
金さんの体を半分隠してしまうほど雪が積もっていても、一歩一歩転んでは起き上がり、また転んでは起き上がり、一日がかりで山を登り、下りてくるのです。
時おり訪れる日本の人をみつけては、手をとり、話すことがありました。
「私の神さまはね、方子さまなんですよ。韓国の障害者やその家族は、方子さまのことを決して忘れず、語り継いでいくことでしょう。本当に、ありがとう。妃殿下、今日は日本の方が見えてよかったですね。久しぶりに故郷の話をされましたか?」
こうして方子さまのお心は、金寿妊さんの温かい手によって受け継がれていきました。
ワールドカップという大きな舞台の片隅で、金さんが心を込めて作ったペナントには、日本と韓国の国旗が今も仲良く並んでいます。
国旗の間に描かれたリボンは、二人の思いが時を超え、まるで一羽のチョウとなってそこに舞いおりたようでした。
スタジアムにかざられることはありませんでしたが、この大会に出場したすべての国に配られました。
今ごろ、世界中のどこかでそっと、風にゆれているのかもしれませんね。
完
お話の投稿者 天乃悠
この作品は、読者からの投稿作品です。
福娘の姉妹サイト |
| 366日への旅 毎日の記念日などを紹介 |
| 福娘童話集 日本最大の童話・昔話集 |
| さくら SAKURA 女の子向け職業紹介など |
| なぞなぞ小学校 小学生向けなぞなぞ |