福娘童話集 > きょうの世界昔話 > その他の世界昔話 >プシケとアモール
第211話
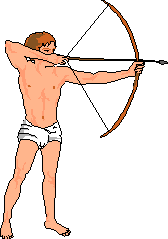
プシケとアモール
ギリシア神話 → ギリシアの情報
※本作品は、読者からの投稿作品です。 投稿希望は、メールをお送りください。→連絡先
制作: フリーアナウンサーまい【元TBS番組キャスター】
※本作品は、読者からの投稿作品です。 投稿希望は、メールをお送りください。→連絡先
投稿者 クララの眠れる朗読チャンネル
※本作品は、読者からの投稿作品です。 投稿希望は、メールをお送りください。→連絡先
制作: Koto’s Sweet Dreams Channel
むかしむかし、ある国の王様に、美しい三人のお姫さまがいました。
三人のお姫さまの中でも末のお姫さまのプシケは、特に美しくて女神の様です。
そのプシケを一目見たいと、遠い国からもたくさんの人がやって来ました。
さて、これを知った美の女神ヴィーナスはかんかんに怒り、自分の息子のアモールという神さまに言いました。
「お前の魔法の弓で、あの娘をひどいめにあわせておくれ。・・・そうだね、この世で一番みにくい男が好きになるようにね」
アモールの弓矢には不思議な力があって、矢に当たった者は一番最初に見た人を好きになってしまいます。
アモールはヴィーナスの命令に従ってプシケをこらしめに出かけましたが、けれどプシケを一目見た時からプシケの事が好きになってしまったのです。
そこでアモールはプシケがヴィーナスに見つからないように、プシケをたった一人ぼっちで、さみしくお城に閉じこめてしまいました。
王さまとおきさきさまは、娘のプシケをとても心配して、太陽の神アポロンに尋ねました。
「アポロンさま、どうすれば、娘が幸せになるのでしょうか?」
すると、アモールからこっそり頼まれていたアポロンは、こう答えたのです。
「プシケを、岩山のてっぺんに一人で置いておきなさい。そうすれば、翼のあるヘビがやって来て、自分のお嫁さんにする為に連れて行くだろう」
「大切な娘を、翼のあるヘビのお嫁に!」
それを聞いた王さまとおきさきさまは、すっかり悲しみました。
けれど、プシケは言いました。
「アポロンさまの命令ですもの。きっと大丈夫です。わたしは一人で岩山へ行きます」
そして王さまもおきさきさまは、娘を一人岩山に残して、泣く泣くお城へ帰っていきました。
さて、岩山に残されたプシケのまわりには、だんだん暗い闇がおりてきました。
プシケは、恐怖で泣きそうになりました。
ところがその時、気持ちのよい西風が吹いてきたかと思うと、プシケの体は、ふわりと空に浮かび上がったのです。
プシケは気がつくと、まぶしい朝の光の中に立っていました。
そばには、川が流れ、岸には美しいお城がたっています。
お城の柱は金で、壁は銀、そして床には宝石がちりばめてあります。
プシケがお城の入り口立っていると、どこからか声がしました。
「これがあなたのお城です。怖がらずに、お入りなさい。食事の用意をいたしましょう。わたしたちはあなたの召使い。
どんな事でもお言いつけください」
お城の中には、見た事もないごちそうがならんでいました。
どこからか、楽しい音楽も聞こえてきます。
けれど、だれの姿も見えません。
そして夜になると、男の人の声が聞こえました。
「わたしの姿は見えないでしょうが、どうか友だちになってください」
それは、姿を消したアモールでした。
アモールの声はやさしく親切で、プシケはアモールの事が好きになっていました。
ある日、声は言いました。
「どうか、ぼくのおきさきになってください」
「はい」
それからプシケは、とても幸せでした。
お婿さんは声だけですが、話しているだけで楽しい毎日です。
そんなある日、プシケの二人のお姉さんが、お城を探しあてて訪ねてきました。
「まあプシケ、あなたのお婿さんは、声だけなの? 姿が見えないなんて、魔物かもしれないわ。今はやさしくても、いつか正体を現して、あなたを食べてしまうかもしれないわよ」
お姉さんたちの言葉に、プシケはすっかり心配になってしまいました。
そしてお姉さんたちは、
「ナイフとランプを、ベッドの下に隠しておくのよ。真夜中にそっと起きて、お婿さんの顔を見てごらんなさい。そしてもし魔物だったら、ナイフで刺しておしまい」
と、言うと、帰っていきました。
プシケはさんざん悩みましたが、とうとうお姉さんたちに言われた通り、真夜中に起き上がると、震える手でランプとナイフを持って、アモールの眠っているベッドの中の顔をのぞきました。
「まあ、あなたは」
それは、見た事もないほど美しい若者のアモールでした。
それに気づいたアモールも、目を覚ましました。
「ごめんなさい。お姉さんたちに言われて、あなたを魔物ではないかと疑っていたの。許してください」
「いや、母に知られないように、姿を見せなかったぼくが悪いんだ。ぼくは勇気を持って、母のヴィーナスにあなたとの結婚を許してもらうよ」
そしてアモールはヴィーナスを説得して、プシケを許してもらい、プシケとアモールはいつまでも幸せに暮らしたということです。
おしまい
福娘の姉妹サイト |
| 366日への旅 毎日の記念日などを紹介 |
| 福娘童話集 日本最大の童話・昔話集 |
| さくら SAKURA 女の子向け職業紹介など |
| なぞなぞ小学校 小学生向けなぞなぞ |

