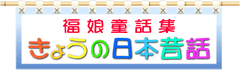
福娘童話集 > きょうの日本昔話 > 6月の日本昔話 > 百物語
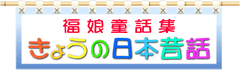
福娘童話集 > きょうの日本昔話 > 6月の日本昔話 > 百物語
6月18日の日本の昔話
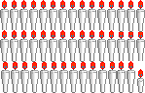
百物語
むかしむかし、江戸の浅草花川戸(あさくさはなかわど)に、道安(どうあん)という医者が住んでいました。
ある日のこと。
《伝法院(でんぽういん)の広間(ひろま)で、百物語(ひゃくものがたり→詳細)をもよおすので、ぜひご出席いただきたい》
と、いう、つかいがきました。
伝法院(でんぽういん)といえば、浅草境内(あさくさけいだい)にある、ゆいしょある大きな寺です。
日がくれると、道安は寺へでかけていきました。
この伝法院には、小堀遠州(こぼりえんしゅう→江戸前期の有名な茶人・造園家)がつくったといわれる、江戸でも名高い、りっぱな庭がありました。
この庭を前にして、広間には、九十九本のローソクが立てられています。
そして、その一本一本のローソクのうしろには、九十九人の男女が、きちんとすわっているのでした。
年はさまざまでしたが、男も女も礼儀ただしくすわっているところをみると、みんな、そうとうな格式(かくしき→身分や家柄がすぐれていること)を持った人たちのように思われます。
「どうぞ、こちらへ」
道安は庭が正面に見える、一座のなかの上座(かみざ→目上の人がすわる場所)にすわらされました。
紋(もん)つき羽織(はおり)に、はかまをはいた、世話役らしい老人が、しらが頭をていねいにさげて、こういいました。
「では百人、ちょうどそろいましたので、会をひらかせていただきます。今夜はじめてご出席のかたもおられますので、ちょっともうしのべますが、この百物語は、おひとりが一つずつ、ばけものの話をなさって、ご自分の前のローソクを消してまいります。そういたしますと、百本のローソクが消されましたとき、ほんとうのばけものがあらわれるのでございます」
と、そのとき、道安はカラカラと笑って、
「この世にばけものなど、おろうはずはない。もしおったら、死んでもよいからお目にかかりたいものじゃ」
と、いいました。
すると、広間じゅうのローソクがパッと消えると同時に、そこにいた九十九人が、ひとりのこらずすがたを消してしまったのです。
おしまい