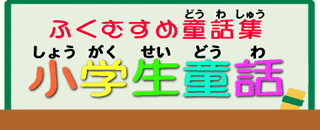| メ ニ ュ ー 福娘童話集 |
| ・6年生の日本昔話 |
| ・6年生の世界昔話 |
| ・6年生の日本民話 |
| ・6年生のイソップ童話 |
| ・6年生の えど 小話 |
| ・小学生童話へ |
6年生の日本民話
オオカミばあさん
京都府の民話
| ♪音声配信(html5) |
| 朗読者 : スタヂオせんむ |
むかしむかし、たびたびのききん(→不作のために食べものがたりなくなること)にくわえ、わるい病気がはやって、村人たちがおおぜい死んだことがあります。
丹波(たんば→京都府)の山あいの村に、スギというおばあさんがすんでいました。
「ああ、うちにも孫がでけた。ええ男の子や」
そういってよろこんだのもつかのまで、ある年の秋、息子と嫁(よめ)とかわいい孫が、あいついで死んでしまったのです。
一人っきりになったおばあさんは、生きる気力をなくしてしまい、
「生きていてもしかたねえ、はよう、わしも死なしてくれえ」
と、ただ泣いてくらしていました。
まもなく冬がきて、山に雪がふりはじめたころ、おそろしいオオカミが里のほうへおりてきました。
そして子どもがオオカミに食い殺されたので、村人たちは大さわぎです。
おスギばあさんが人前に姿(すがた)を見せなくなったのは、そのころからでした。
と、いっても、決していなくなったわけではなく、夜になると家には明かりがつきましたし、かまどのけむりもあがります。
そのころ、村にはおそろしいうわさが広がりました。
「あのばあさん、オオカミをかっとるんや」
「そうそう、朝晩(あさばん)、オオカミにごはんをたべさしているそうだ」
うわさはうそではないらしく、夜ごとにウォーンという、オオカミの鳴き声がすぐ近くで聞こえ、月あかりの庭さきを通っていく黒いけものを、何人もの村人が見たのです。
そこである晩(ばん)、男たちが火なわ銃(ひなわじゅう)を持って、おスギばあさんの家の近くへいってみました。
ひっそりとした家に、 あんどんのあかりがともっていました。
そのあかりで、しょうじに大きくおばあさんとオオカミのかげがうつりました。
鉄砲(てっぽう)をもった男たちは、みな足がすくんでしまい、
「あれにとびかかられては、このくらい夜のこと、ズドンとうつまもないぞ」
と、ぞろぞろにげてかえりました。
それからしばらくしたある日、おスギばあさんがめずらしく外へでかけると、お坊(ぼう)さんをつれて戻(もど)って来ました。
お坊(ぼう)さんは土間(どま→家の中でゆかをはらず、土のままにしてある所。主に台所)からとびだしてきたオオカミを見てビックリしましたが、そのオオカミにむかって、おばあさんがいいました。
「わしなあ、お前が家のうらまできた日には、『はようわしをたべてくれ、息子や孫のところへいかしてくれ』そうおもうて戸をあけたんや。そやけどお前は、このわしをたべなんだ。わしがたいたごはんをたべて、いままでいてくれた。おかげで、きょうまで命をながらえることができた。お前には礼をいわんならん。だども、いつまでもというわけにはいかん。ありがたいお経を聞いて、山のなかまのところへかえってくれ」
「えっ、おほん。それならオオカミや、よう聞くがええ」
お坊(ぼう)さんは、あがりがまち(→家のあがり口)に立って、お経をとなえだしました。
オオカミはキバをむいて土間を歩きまわっていましたが、しだいにおちついて、お坊(ぼう)さんのまえにすわりこみました。
するととつぜん、耳をつんざく音が、うしろの山のほうまでこだましたのです。
しょうじのかげには、鉄砲(てっぽう)をかまえたおばあさんが立っていました。
土間には血にそまったオオカミがいて、もう死んでいました。
「なんぼわけがあるいうても、お前は村の子どもや旅の人をおそうた。つらいけど、わしはこうするしかなかったんや。ごめんな」
おばあさんの目から、なみだがあふれておちました。
そしてお坊(ぼう)さんの手をかりて、オオカミのなきがらを山へはこぶと、てあつくほうむりました。
こののち、村ではだれ一人オオカミにおそわれるものはなかったそうですが、おスギばあさんはその日いらい姿(すがた)をけして、二度と村には戻(もど)ってこなかったという事です。
おしまい
| 福娘のサイト 366日への旅 |
毎日の素敵な記念日をイラスト付きで紹介。 |
毎日の誕生花を花写真付きで紹介。 |
| きょうの誕生日・出来事 有名人の誕生日やその日の出来事と性格判断 |
| 福娘のサイト 子どもの病気相談所 |
| 子どもの病気相談所 病気検索と対応方法、症状から検索するWEB問診 |
| 福娘のサイト 世界60秒巡り |
| 世界60秒巡り 世界の国旗・国歌・国鳥・観光名所などを紹介。 |
| 世界遺産巡り 日本と世界の世界遺産を写真付きで紹介。 |
| 都道府県巡り 47都道府県の豆知識。 県章、県鳥、県花、観光名所など。 |