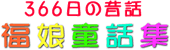| - 広 告 - |
福娘童話集 > 日本のこわい話(百物語)
百物語 第16話
朝顔
東京都の民話 → 東京都情報
| ♪音声配信 |
| スタヂオせんむ |
むかしむかし、江戸(えど→東京都)に、岡田弥八郎(おかだやはちろう)という侍(さむらい)が住んでいました。
弥八郎(やはちろう)には、ただ一人の娘がいて、その名をしずと言います。
しずは朝顔の花が大好きで、十四才の時に朝顔のつぼみを見つけて、こんな歌をつくりました。
♪いかならん
♪色に咲くかと
♪あくる夜を
♪待つのとぼその
♪朝顔の花
父はこの歌をたんざくに書いて、妻に見せました。
「あの小さな胸に、どんな色に花が咲くであろうと、次の朝を待つ心じゃ」
「はい、まこと素直に、うたわれております」
ところが娘のしずは、この年の冬にかぜをこじらせて、そのまま死んでしまったのです。
残された父と母は、とても悲しみました。
さて、夏も近いある日の事。
母がなにげなく娘の手箱(てばこ→小物入れ)を開けてみると、中には小さな紙包みがいくつも入っていました。
そしてどの包みにも細いきれいな字で、桃色、空色、しぼり(→青色の一種)などと、色の名が書き記されていました。
一色ずつ紙にていねいに包んだ、その色の朝顔の種です。
(ああ、娘はこの種をまいて、それぞれの色の美しい花の咲くのを、どれほど見たかった事でしょう)
そう思うと母はたまらなく、せつなくなりました。
「そうだわ。せめてこの種をまいて、娘をとむらいましょう」
母は庭に、その朝顔の種をまきました。
日がたってつるが伸び、やがてつぼみがつきました。
ある夏の朝、弥八郎(やはちろう)を仕事に送り出した母は、ふと庭の朝顔を見ました。
すると美しい一輪の花がパッと咲いていて、その花のそばに娘のしずが立っているではありませんか。
「おおっ、しず、しずかい?」
母が思わず声をかけると、娘はうれしそうにニッコリほほ笑み、そして小さな声で、
「お花をありがとう」
と、言って、そのままスーッと消えてしまいました。
夕方になって父の弥八郎(やはちろう)が帰って来た時、夕方にはしぼむはずの朝顔は、まだ美しい色で咲いていたという事です。
おしまい
| お話しの移動 | |||||||||||||||||||||||||||
・ 福娘童話集 百 物 語 ・ 1話 〜 10話 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ジャンルの選択 | |||||||||||||||||||||||||||
|