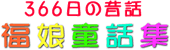| - 広 告 - |
福娘童話集 > 日本のこわい話(百物語)
百物語 第301話
魂のある人形
東京都の民話 → 東京都情報
むかしむかし、江戸のある町の料理屋で、三代春(みよはる)という三十歳になる女の人が働いていました。
あるとき、三代春はお客から小さな人形をもらいました。
三代春はこの人形が大変気に入り、自分で着物をつくっては人形に着せて、わが子のように可愛がっていました。
ところがあるとき、どうしてもお金に困る事があって、三代春は人形に何枚もの着物を着せて絹の布に大事につつむと、立派な木の箱に入れて質屋さんにあずけて、お金を借りました。
そして人形をそのままにして、三代春は次の年の年末にお店をやめてしまいました。
そして十数年ぶりに実家にもどり、母親と一緒にくらしはじめたのです。
それから数ヶ月たった、春の夜のことです。
三代春は、不思議な夢をみました。
お店にいたときに可愛がっていた人形が夢にあらわれて、こんなことをいうのです。
「あなたは、お店をやめて、お母さんと楽しくくらしていますが、わたしは何枚も着物を着せられて、そのうえ絹の布でぐるぐる巻きにされて、暑さと息苦しさで着物のそでを食いちぎって、やっと息をしています。早くまっ暗な質屋の蔵から出してください。ああ、暑い。ああ、苦しい。早く、早く」
娘がうなされている声を聞いて、母親は三代春を起こしました。
そして娘から、人形の話を聞いた母親は、
「お前は、なんてことを。いいかい、人形にはたましいがあるんだよ。それをそのまま質屋の蔵なんかに入れておくなんて、うらまれたらどうするんだね。お金がないのなら、兄さんの市蔵(いちぞう)に頼んで、早く出してもらおう」
そういって、ほかの町にすむ三代春の兄のところへ出かけていきました。
市蔵は母親の話を聞くと、すぐに質屋へ行ってお金をかえし、妹の三代春があずけていた人形を蔵から出してくれたのです。
市蔵は店先で、ひきとった人形の木箱を開いてみました。
くるんである絹の布をとくと、三代春の夢の話通り、人形のそでが食いちぎられていたそうです。
おしまい
| お話しの移動 | |||||||||||||||||||||||||||
・ 福娘童話集 百 物 語 ・ 1話 〜 10話 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ジャンルの選択 | |||||||||||||||||||||||||||
|