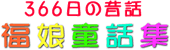| - 広 告 - |
福娘童話集 > 日本のこわい話(百物語)
百物語 第207話

ならず者と白いヘビ
千葉県の民話 → 千葉県情報
むかしむかし、ある小さな里に、長さが一メートルほどの白いヘビが二匹でてきました。
二匹の白いヘビは人をおそれるようなことも、人に悪さをするようなこともありませんでした。
二匹は毎日のように、仲よく里の中をはいずっていました。
「このヘビたちは、つがい(→夫婦)かのう。とても仲がよい。二匹ともまっ白とは、ほんにめずらしい」
「白いヘビは神さまの使いだというぞ。それが一度に二匹も現れたんじゃ。この里に何かいいことがあるかもしれんな」
里の人たちは、とつぜん現れた白いヘビを、そっとしておいてやりました。
ところがこの里には、八郎次(はちろうじ)というならず者がいました。
自分には何もこわいものはないと、いつも強がりをいっています。
八郎次は白いヘビの話を耳にすると、みんなの見ている前で二匹のヘビをつかみあげて、たたき殺してしまったのです。
「ヘビが何をしたというんじゃ! 何もせんのに、殺すことはなかろう」
お百姓(ひゃくしょう)の一人がいうと、
「ふん! 殺すのはかってだろう。目玉の赤い白いヘビなど、気持ちわるくてしょうがねえ」
「白いヘビはな、神さまのつかいだ。たたりがあったらどうする!」
「なにがたたりじゃ。そんなもんはこわくない」
朝から酔っぱらっている八郎次は、そのまま家に帰っていきました。
その夜の事です。
八郎次の顔は、まるで皮をむいたトウガン(ウリの一種)のように、まっ白にふくれあがってしまったのです。
顔ばかりではありません。
手も足も、体中が白くなってふくれあがり、はげしい痛みにおそわれたのです。
八郎次は家から飛び出すと、
「痛え! 痛えよう! 助けてくれー!」
と、さけびながら、里じゅうを走りまわりました。
そして三日三晩苦しみぬいて、やぶの中で死んでしまいました。
おしまい
| お話しの移動 | |||||||||||||||||||||||||||
・ 福娘童話集 百 物 語 ・ 1話 〜 10話 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ジャンルの選択 | |||||||||||||||||||||||||||
|