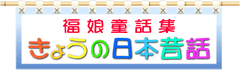
福娘童話集 > きょうの日本昔話 > 7月の日本昔話 > きりきりのぜんべいさん
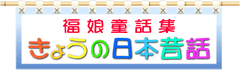
福娘童話集 > きょうの日本昔話 > 7月の日本昔話 > きりきりのぜんべいさん
7月6日の日本の昔話
きりきりのぜんべいさん
むかしむかし、きりきりとよばれていた田舎(いなか)に、お人好しで、働き者のぜんべいさんという人がいました。
ある日のことです。
ぜんべいさんが草刈りをしていますと、
「ぜんべいさん、ぜんべいさん」
と、近くの沼から声がします。
見ると、沼の中で女の人が、おいでおいでをしているではありませんか。
「あれ、おらに用事か?」
ぜんべいさんが近づくと、女の人はこういいました。
「ぜんべいさん、わたしがお金を出すから、村の人たちとお伊勢参り(おいせまいり)に行ってください。そのかわり帰り道に、わたしの姉にこの手紙を渡してください」
女の人は姉が住んでいるという、遠い沼(ぬま)の話をして、手紙と財布(さいふ)を、ぜんべいさんに渡しました。
「その財布の中には、百文(ひゃくもん→三千円ほど)のお金が入っていますが、使うときに、一文だけ残しておくと、あくる日には、また、百文になっていますから」
と、いうと、そのまま消えてしまいました。
(夢ではあるまいか?)
手紙と財布をにぎったぜんベいさんは、これはえらいことだと思いました。
なにしろ、ぜんべいさんのおかみさんはケチで、お伊勢参りにいくと言うと、反対するに決まっています。
でも、家に帰ったぜんべいさんは、思いきって、
「おら、お伊勢参りにいくべ」
と、いうと、
「おまえ、気でもちがったのかね! うちは貧乏でお金もないのに!」
と、おかみさんにどなられました。
でも、ぜんべいさんはこっそり、村の人たちとお伊勢参りに出かけたました。
きりきりという所からお伊勢さんまでは、それは遠い旅でしたが、ぜんベいさんはお金には困りません。
いわれたとおり、一文を財布に残しておくと、あくる日には、百文のお金が入っています。
こうして、村の人たちとお伊勢参りをすませると、
「おら、用事があるから・・・」
と、ぜんべいさんはみんなと別れて、沼をさがしに出かけました。
とうげをこえ、キツネの出そうな山道を通って、やっと沼へつくと、
(ははん、この気味の悪い沼に、姉さがいるんだベ)
教えられたとおり、タン、タンと手を打つと、沼が急に金色に光って、きれいな姉が出てきました。
手紙を渡すと、姉はうれしそうにいいました。
「おかげで、妹のことがよくわかりました。妹にもわたしの手紙を届けておくれ」
姉は沼の中から、たくましいウマを連れてきて、
「さ、手紙を持ち、このウマに乗って、村の人たちに追いついておくれ、そのかわり、必ず目をつむっているのですよ」
ぜんべいさんが姉のいうとおりにすると、パカパカパカパカと、走り続けたウマが、ピタリと止まりました。
「ウヒャー! ぜんベいさん、どこからきたのだ?」
目をあけると、村の人たちがいて、ウマの姿はもう消えていました。
さて、旅から帰ったぜんベいさんは、沼にとんでいって、お伊勢参りのお礼をいって手紙を渡しました。
すると、沼の女の人はとても喜んで、ぜんべいさんに小さな石の臼(うす)をくれました。
「米粒を一粒入れて、ガラリと一回回すと、金の粒が出てくるふしぎな臼です。そのかわり、必ず、一日一回だけ臼を回しておくれ」
家に帰ったぜんベいさんが、小さな石の臼を神棚(かみだな)にあげておがんでいたので、おかみさんは気でもくるったのかと大笑いしました。
でも、ぜんベいさんは一日に一回だけ、米粒を入れて臼をひき、金持ちになりました。
それを見ていたおかみさんは、
「もっと回せば、もっと金持ちになるだろう」
と、米粒をいっぱい入れて、ガラリガラリと臼をひくと、臼がドスンところがって、ころがって、ころがって、ついにあの沼の中に落ちてしまったということです。
おしまい