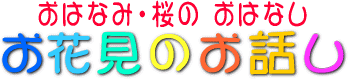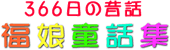| 福娘童話集メニュー |
・福娘童話集 ホーム ・せっくのおはなし |
福娘童話集 >お花見・桜のお話し > お花見について
お花見について

お花見の始まり
お花見の起源は、奈良時代に中国から伝来した梅を貴族たちが観賞した事が始まりだと言われています。
その為に、当時のお花見は梅の花が中心でした。
それが平安時代になると梅よりも桜の人気が上昇し、お花見と言えば桜の花見となりました。
記録に残る日本最古のお花見は、嵯峨天皇が812年(弘仁3年)に神泉苑にてもよおした『花宴の説』だと日本後紀に記されています。
庶民のお花見
嵯峨天皇以降、お花見は天皇主催の定例行事として行われました。
それに習って戦国大名の間でもお花見が流行して、豊臣秀吉も1598年(慶長3年)3月15日に醍醐寺の三宝院で醍醐の花見と呼ばれる大規模なお花見を行っています。
ただ、一般庶民がお花見をする事はまずありませんでした。
お花見が庶民に広く広まっていったのは江戸時代で、徳川吉宗が江戸の各地に桜を植えさせたのがきっかけです。
花より団子
花より団子と言うことわざがある様に、お花見の定番アイテムは花見団子です。
花見団子は、江戸時代の庶民から広まったと言われています。
花見団子の色は一般的に桜色・白色・緑色の三色ですが、この色にはそれぞれ意味があって、
桜色は、桜を表しています。
白色は、冬の名残りの雪を表しています。
緑色は、春から夏に向けて木が緑色になることを表しています。
| お花見・桜のお話し 6話 |
| ・かるい帰り道 |
| ・かわをむく |
| ・二月の桜 |
| ・彦一とサクラの花 |
| ・きりょうじまん |
| ・安国寺の桜 |
| 福娘のサイト |
| 366日への旅 毎日の記念日・誕生花 ・有名人の誕生日と性格判断 |
| 福娘童話集 世界と日本の童話と昔話 |
| 子どもの病気相談所 病気検索と対応方法、症状から検索するWEB問診 |
| 世界60秒巡り 国旗国歌や世界遺産など、世界の国々の豆知識 |