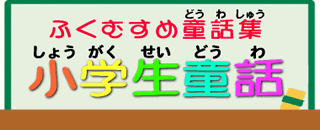| メ ニ ュ ー 福娘童話集 |
| ・6年生の日本昔話 |
| ・6年生の世界昔話 |
| ・6年生の日本民話 |
| ・6年生のイソップ童話 |
| ・6年生の えど 小話 |
| ・小学生童話へ |
6年生の日本民話

牡丹灯籠(ぼたんどうろう)
京都府の民話
| ♪音声配信(html5) |
| 朗読者 ; 創作活動のサイト 『Web団 零点』 |
むかしむかし、京の都の五条京極(ごじょうきょうごく)に、荻原新之丞(おぎわらしんのじょう)という男がすんでいました。
まだ若(わか)い奥(おく)さんに死なれたため、毎日がさびしくてたまらず、お経をよんだり歌をつくったりして、外へも出ないで暮(く)らしています。
七月の十五夜の日の事、夜もふけて道ゆく人もいなくなったころ、二十才くらいの美しい女の人が、十才あまりの娘(むすめ)をつれて通りかかりました。
その娘(むすめ)には、ぼたんの花のとうろう(→あかりをともす器具)をもたせています。
新之丞(しんのじょう)は、美しい女の人に心をひかれて、
(ああ、天の乙女(おとめ)が、地におりてきたのだろうか)
と、つい家をとびだして、ついていきました。
新之丞(しんのじょう)が声をかけると、女はいいました。
「たとえ月夜でも、かえる道はおそろしくてなりません。どうかわたくしを、送ってくださいますか?」
「よろしければ、わが家へきて、ひと晩(ばん)おとまりなさい。遠慮(えんりょ)はいりませぬ。さあどうぞ」
そういって新之丞(しんのじょう)は女の手をとり、家へつれてもどりました。
新之丞(しんのじょう)が歌をよむと、女もすぐにみごとな歌でかえすので、新之丞(しんのじょう)はうれしくてたまりません。
すっかりしたしくなって、時がたつのもわすれるうちに、東の空があかるくなりかけました。
女はいそいそとかえっていきましたが、それからというもの、女は日がくれると必ずたずねてきました。
ぼたんの花のとうろうを、いつも娘(むすめ)にもたせて。
新之丞(しんのじょう)のほうも、毎日、女が来るのが楽しみでなりません。
そして、二十日あまりが過ぎました。
たまたま家のとなりに、物知りなおじいさんが住んでいました。
「はて、新之丞(しんのじょう)のところは一人きりのはずだが、毎晩(まいばん)若(わか)い女の声がしておる。うむ、・・・どうもあやしい」
おじいさんはその夜、かべのすきまから新之丞(しんのじょう)の家の中をのぞきました。
すると新之丞(しんのじょう)があかりのそばで、頭から足のさきまでそろった白いガイコツと、さしむかいですわっているのです。
新之丞(しんのじょう)が何かしゃべると、ガイコツがうなずきます。
手やうでの骨(ほね)も、ちゃんとうごかします。
そのうえガイコツは口のあたりから声を出して、しきりに話をしているのでした。
あくる朝、おじいさんは新之丞(しんのじょう)の所へ行き、たずねました。
「そなたのところへ、夜ごとに女の客があるらしいが、いったい何者じゃ?」
「・・・・・・」
新之丞(しんのじょう)は、こたえません。
それで、昨夜見たとおりのことを話したうえで、
「近いうち、そなたの身にきっとわざわいがおこりますぞ。死んでゆうれいとなり、いつまでもこの世でまよい歩いているものと、あのようにつきおうておったら、精(せい)をすいつくされて、わるい病気にむしばまれます」
これには新之丞(しんのじょう)もおどろいて、今までの事をありのままをうちあけたのでした。
「さようであったか。その女が万寿寺(まんじゅじ)のそばに住んでおるというたのなら、いってさがしてみなされ」
「はい、わかりました」
新之丞(しんのじょう)はさっそく、五条(ごじょう)から西へ、万里小路(までのこうじ)までいってさがしました。
しかし一人として、それらしい女を知る人がありません。
日がしずむころ、万寿寺(まんじゅじ)の境内(けいだい)へ入って休み、北のほうへ足をむけると、死者のなきがらをおさめた、たまや(→たましいをまつるお堂)が一つ、目にとまりました。
古びたたまやで、よく見たところ、棺(ひつぎ)のふたにだれそれの息女(そくじょ→みぶんのある娘(むすめ)をさす言葉)なになにと、戒名(かいみょう→死者につける名前)が書きつけてありました。
棺(ひつぎ)のわきに、おとぎぼうこ(→頭身を白い絹(きぬ)で小児の形に作り、黒い糸を髪(かみ)として左右に分け、前方に垂(た)らした人形)、とよばれる子どもの人形が一つ、また棺(ひつぎ)のまえには、ぼたんの花のとうろうがかかっていました。
「おお、まちがいなくこれじゃ。このおとぎぼうこが娘(むすめ)にばけていたのだな」
新之丞(しんのじょう)はこわくなって、走ってにげかえりました。
家へもどったものの、夜にまた来るかとおもうと、おそろしくてたまりませんので、となりのおじいさんの家にとめてもらいました。
それからおじいさんに教わって東寺(とうじ)へいき、そこの修験者(しゅげんじゃ→山で修行する人)にわけをうちあけて、
「わたくしは、どうしたらよいのですか?」
と、たずねました。
「まちがいなく、新之丞殿(しんのじょうどの)は、バケモノに精をすいとられておられますな。あと十日も、いままでどおりにしておったら、命もなくなりましょう」
修験者はそういって、まじないのおふだを書いてくれました。
そのおふだを家の門にはりつけたところ、美しい女も、とうろうをもった娘(むすめ)も、二度とすがたを見せなくなったのです。
それから、五十日ほどが過ぎました。
新之丞(しんのじょう)は東寺へでかけて、今日までぶじに過ごせたお礼をしました。
この日はお供(とも)の男を一人つれていたので、東寺を出てお酒を飲みましたが、お酒を飲むと、むしょうに女に会いたくなって、お供(とも)の男が止めるのも聞かず、万寿寺(まんじゅじ)へ出かけていったのです。
万寿寺(まんじゅじ)に着くと、あの女が現れ、
「毎晩(まいばん)、お会いしましょうと、あれほどかたくお約束をしましたのに、あなたさまの気持ちがかわってしまい、それに東寺の修験者にもじゃまをされて、ほんとうにさみしゅうございました。・・・でも、あなたさまは来てくだされました。お目にかかれて、ほんとうにうれしゅうございます。どうぞこちらへ」
「うむ、そなたにつらい思いをさせるとは、まことにすまんことをした」
新之丞(しんのじょう)は女に手を取られて、そのまま奥(おく)のほうへつれていかれました。
後をつけてきたおともの男は、こしをぬかすほどビックリして、
「た、たっ、大変だ! 新之丞(しんのじょう)さまが、あの女にさそいこまれて寺の墓地のほうへ!」
と、となり近所にいってまわりました。
それで大さわぎになり、みんなして万寿寺(まんじゅじ)の北がわの、たまやがあるところへいってみました。
しかし新之丞(しんのじょう)は棺(ひつぎ)のなかへひきこまれて、白骨(はっこつ)の上へ重なるようにして死んでいました。
女に精を吸い取(すいと)られて、新之丞(しんのじょう)は老人のようにやつれていましたが、その口には笑みが浮(う)かんでいました。
万寿寺(まんじゅじ)では気味悪くおもって、そのたまやをべつの場所へうつしました。
しばらくして、雨がふる夜には新之丞(しんのじょう)と若(わか)い女が、ぼたんの花のとうろうをもった娘(むすめ)とともに京の町を歩く姿(すがた)が見られ、それを見たものは重い病気にかかるとうわさが立ちました。
新之丞(しんのじょう)の親類(しんるい)の人たちが、手厚く供養(くよう)をしましたが、たましいがまよい歩かないようになるまでには、かなりの時間がかかったという事です。
おしまい
| 福娘のサイト 366日への旅 |
毎日の素敵な記念日をイラスト付きで紹介。 |
毎日の誕生花を花写真付きで紹介。 |
| きょうの誕生日・出来事 有名人の誕生日やその日の出来事と性格判断 |
| 福娘のサイト 子どもの病気相談所 |
| 子どもの病気相談所 病気検索と対応方法、症状から検索するWEB問診 |
| 福娘のサイト 世界60秒巡り |
| 世界60秒巡り 世界の国旗・国歌・国鳥・観光名所などを紹介。 |
| 世界遺産巡り 日本と世界の世界遺産を写真付きで紹介。 |
| 都道府県巡り 47都道府県の豆知識。 県章、県鳥、県花、観光名所など。 |