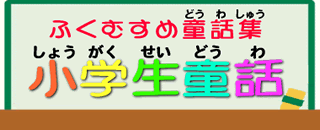| メ ニ ュ ー 福娘童話集 |
| ・6年生の日本昔話 |
| ・6年生の世界昔話 |
| ・6年生の日本民話 |
| ・6年生のイソップ童話 |
| ・6年生の えど 小話 |
| ・小学生童話へ |
6年生の江戸小話(えどこばなし)

ぞうきんとお年玉
あるところに、何ごとにも、えんぎをかつぐだんながいました。
そのおかげか、店ははんじょうしています。
ある年の、大みそかのこと。
だんなが、店のものにいいました。
「あしたは、めでたいお正月じゃ。お正月の神さまをおむかえするのだから、いつもより、ねんいりにそうじをしなさい」
この店に、はたらきものの女の人がいました。
名前を、「おたけさん」といって、だれよりもはたらくのですが、そそっかしいのが玉にきずです。
「すみからすみまで、ぞうきんをかけよっと」
おたけさんがはりきって、床の間(とこのま)をふいていたときです。
「すまないが、おつかいにいってきておくれ」
おかみさんがたのみました。
そそっかしいおたけは、ぞうきんを床の間(とこのま)においたまま、おつかいに飛び出していってしまいました。
おつかいから帰ったおたけは、ぞうきんがけがおわっていないのをわすれて、だいどころしごとをはじめてしまいました。
さて、元旦の朝。
だんなが、床の間(とこのま)のかけじくを、おめでたい『七福神(しちふくじん)』に、とりかえようとすると、よごれたぞうきんが、ポンとおいてあるではありませんか。
だんなは、カンカンにおこりました。
「正月というのに、こんなものをおくなんて、えんぎでもない。さては、おたけのしわざだな。おたけ!」
おたけをよんで、しかりつけました。
すると、とんちのきくこの店の番頭(ばんとう)が、
「だんなさま。ぞうきんは、えんぎが悪いだなんて、とんでもありません」
と、口をはさみました。
「なに。よごれたぞうきんなのに、えんぎがいいとは、どういうわけだ」
「はい。ぞうきんを、あて字で書けば、蔵(ぞう→くら)と金(きん→かね)。蔵(くら)に金(かね)がたまるというわけです」
番頭にいわれて、だんなは大よろこびです。
「なるほど。これは、えんぎがいいわい」
だんなは番頭とおたけに、お年玉をたくさんあげたのでした。
おしまい
| 福娘のサイト 366日への旅 |
毎日の素敵な記念日をイラスト付きで紹介。 |
毎日の誕生花を花写真付きで紹介。 |
| きょうの誕生日・出来事 有名人の誕生日やその日の出来事と性格判断 |
| 福娘のサイト 子どもの病気相談所 |
| 子どもの病気相談所 病気検索と対応方法、症状から検索するWEB問診 |
| 福娘のサイト 世界60秒巡り |
| 世界60秒巡り 世界の国旗・国歌・国鳥・観光名所などを紹介。 |
| 世界遺産巡り 日本と世界の世界遺産を写真付きで紹介。 |
| 都道府県巡り 47都道府県の豆知識。 県章、県鳥、県花、観光名所など。 |