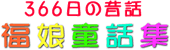| 福娘童話集メニュー |
・福娘童話集 ホーム ・お正月のお話 ・お正月について |
福娘童話集 > お正月のお話し >お正月について
お正月の昔話
お正月について
・お正月とは
あたらしい年の始まりをお祝いする行事で、一般的には1月1日〜1月3日までをお正月と呼びます。
お正月には『初詣(はつもうで)』に行ったり、『おせち料理』を食べたり、子どもたちの大好きな『お年玉』があったりします。
ここでは、そのお正月に関するイベントを説明します。
初詣(はつもうで)
・初詣とは
年が明けてから初めて寺社(しゃじ→神社・寺院)や教会にお参りして、一年の無事と平安をお願いする行事です。
初参りともいいます。
お年玉
・お年玉とは、
お正月に、新年を祝うためにおくる品物の事です。
今では、子どもにおこずかいをあげる意味に使われています。
一般的にお年玉をあげる年齢は、子どもが就職するまでと言われています。
初夢(はつゆめ)
・初夢とは
新年に見る夢で、その年の運を占う事です。
初夢を見る日は地方によって違い、一般的には1月2日の夜から1月3日の朝に見る夢ですが、1月1日の夜から1月2日の朝に見る夢を初夢と言うところもあります。
初夢で見ると縁起の良い物として、「一富士(いちふじ)、二鷹(にたか)、三茄子(さんなすび)」があり、一番に富士山の夢、二番目に鷹の出てくる夢、三番目になすびが出てくる夢を見ると縁起がよいとされています。
これには色々な説がありますが、徳川家康の好きな物が、一番目に富士山、二番目に鷹狩り、三番目に初物のなすであった事から生まれた言葉だと言われています。
鏡餅(かがみもち)
・鏡餅とは
日本に伝わる三つの宝、三種の神器に出てくるカガミの形に似ていることから、鏡餅と呼ばれています。
宝が家にやって来るようにとの意味が込められています。
獅子舞(ししまい)
・獅子舞とは
中国から伝わった踊りで、獅子にふんそうして踊るのが特徴です。
豊作や悪魔払いの意味が込められており、新年の祝いに行われるのが一般的です。
獅子舞にかまれると、やくばらいになると言われています。
はねつき
・はねつきとは
はねつきの羽がトンパの羽ににていることから、トンボが元気よく飛んで虫をつかまえてくれることをあらわしています。
トンボはハチやハエやカなどの害虫を食べるので、厄払いの意味が込められています。
書き初め(かきぞめ)
・書き初めとは
一般的には、正月2日に恵方(えほう→神さまのいる方角)にむかってめでたい意味の言葉を書く事で、一年の初めに気を引きしめ、書道の上達を願う意味が込められています。
門松(かどまつ)
・門松とは
家の玄関にかざる門松には、家に神さまをお迎えするための、家の目印としての意味があります。
おせち料理
・おせち料理とは
おせちとは季節の変わり目を意味する言葉で、季節の変わり目に食べるお祝いの料理をおせち料理と言っていました。
現在では正月に食べる料理だけを、おせち料理と言います。
お正月には好きな物を食べれば良いのですが、むかしから伝わるおせち料理には、定番と言われる食べ物が数多くあります。
それらには、こんな意味が込められています。
田作り(たづくり)
→イワシの稚魚を甘辛く煮た物で、むかしは高級肥料としてイワシが使われていたため、豊作を願って食べられます。
数の子(かずのこ)
→数の子とはニシンの卵で、卵の数が多いことから子孫繁栄を願って食べられます。
黒豆(くろまめ)
→黒色には魔よけの力があるとされ、また豆には「まめに働き」「まめに暮らせる(→健康に暮らせる)という意味があります。
紅白かまぼこ
→紅色と白色の組み合わせは、縁起がよいとされています。
だて巻き
→だて巻きのだては、人気武将の伊達政宗にあやかりたいとの意味で、巻きは巻物(書物)をあらわし、勉強が出来ることを意味しています。
くりきんとん
→くりきんとんはその色形から金のかたまりに見え、裕福になる願いが込められています。
昆布巻き
→こんぶは「よろこぶ」のごろ合わせで、喜びにみちた一年が過ごせるようにとの意味です。
おたふくまめ
→おたふくまめ(お多福豆)は、その文字通り、福が多く来る事を願っています。
ブリの焼き物
→魚のブリは出世魚(しゅっせうお)と言って、成長するにしたがって名前が変わります。その出世魚を食べて、自分たちも出世したいとの意味です。
※ブリの名前 幼魚から順に、ワカシ・イナダ・ワラサ・ブリ(東京地方)
※ブリの名前 幼魚から順に、ツバス・ハマチ・メジロ・ブリ(大阪地方)
タイの焼き物
→魚のタイは、「めでたい」のごろ合わせから来ています。
エビの焼き物
→エビは長いひげとまがった体から、長寿の老人を意味します。エビを食べて、自分たちも長寿になろうとの意味があります。
くわい
→くわいからは大きな芽が出ることから、「めでたい」。芽が出る(→出世する)などの意味が込められています。
レンコン
→レンコンには穴が開いているので、見通しの良い一年になるようにとの願いが込められています。
サトイモ
→サトイモには子イモがたくさんつくことから、子宝への願いが込められています。
おしまい
| お正月のお話し 6話 |
| ・ネコがネズミをおいかける訳 |
| ・どくろをかついで |
| ・三郎の初夢 |
| ・いも正月 |
| ・火正月 |
| ・天福地福 |
| ・お正月について |
| 福娘のサイト |
| 366日への旅 毎日の記念日・誕生花 ・有名人の誕生日と性格判断 |
| 福娘童話集 世界と日本の童話と昔話 |
| 子どもの病気相談所 病気検索と対応方法、症状から検索するWEB問診 |
| 世界60秒巡り 国旗国歌や世界遺産など、世界の国々の豆知識 |