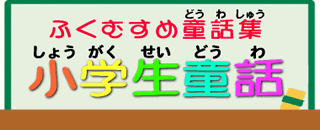| メ ニ ュ ー 福娘童話集 |
| ・6年生の日本昔話 |
| ・6年生の世界昔話 |
| ・6年生の日本民話 |
| ・6年生のイソップ童話 |
| ・6年生の えど 小話 |
| ・小学生童話へ |
6年生の日本昔話
ほんとうの母親
| ♪音声配信(html5) |
| 音声 スタヂオせんむ |
江戸(えど)の下町(したまち)に、おしずと、たいちという親子がすんでいました。
たいちは、ことし十さいになるかわいい男の子でした。
おしずは、たいちをとてもかわいがってそだてていたのです。
ところが、ある日。
とつぜん、おこまという女の人がやってきて、
「おしずさん、たいちはわたしのむすこ。むかし、あなたにあずけたわたしのむすこです。かえしてください」
と、いうのです。
おしずはおどろいて、
「なにをいうのです。あなたからあずかった子は、もう十年も前になくなったではありませんか。このことは、おこまさんだって知っているでしょう」
「いいえ、うそをいってもだめです。おまえさんは、自分の子が死んだのに、わたしの子が死んだといってごまかして、わたしのむすこをとりあげてしまったんじゃありませんか。わたしはだまされませんよ。さあ、すぐにかえしてください!」
おこまは、こわい顔でそういいはるのです。
おしずが、いくらちがうといってもききません。
毎日、毎日、やってきては、おなじことをわめきたてていくのです。
そして、しまいには、顔にきずのある、おそろしい目つきの男をつれてきて、
「はやくかえしてくれないと、どんな目にあうかわからないよ!」
と、おどかすのです。
おしずはこまりはてて、町奉行(まちぶぎょう)の大岡越前守(おおおかえちぜんのかみ)にうったえました。
越前守(えちぜんのかみ)は話をきくと、おこま、おしず、たいちの三人をよびました。
「これ、おこま。おまえは、そこにいるたいちを自分のむすこだといっているそうだが、なにか、しょうこはあるのか?」
「はい。じつはこの子が生まれましたとき、わたしはおちちが出なかったので、おしずさんにあずけたのです。このことは、近所の人がみんな知っています。だれにでもおききになってください」
おこまは、じしんたっぷりにこたえました。
「では、おしずにたずねる。おまえは、おこまの子どもをあずかったおぼえがあるのか?」
「はい。ございます」
おしずは、たいちの手をしっかりとにぎりしめていいました。
「この子が生まれたとき、わたしはおちちがたくさん出ました。それで、おこまさんの子どものひこいちをあずかったのです。でも、その子はまもなく、病気で死んでしまいましたので、すぐにおこまさんに知らせたのでございます」
おしずのことばをきくと、おこまはおそろしい目で、おしずをキッと、にらんでさけびました。
「このうそつき! お奉行(ぶぎょう)さま、おしずは大うそつきです。死んだのはおしずの子です。わたしの子どもをかえしてください!」
「いいえ、死んだのは、たしかにひこいちだったんです。お奉行(ぶぎょう)さま、まちがいありません。おこまの子は死んだのです」
「まだそんなことをいって! 人の子をぬすんだくせに!」
「たいちはわたしの子だよ。だれにもわたしゃしない。わたしのだいじな子なんだ!」
ふたりは、お奉行(ぶぎょう)さまの前であることもわすれて、いいあらそいました。
そのふたりのようすをジッとみつめていた、越前守(えちぜんのかみ)は、やがて、
「ふたりとも、しずまれっ!」
と、大声でしかりました。
おこまとおしずは、あわててはずかしそうに、すわりなおしました。
「おこま。そのむすこがおまえの子どもである、たしかなしょうこはないか? たとえば、ほくろがあるとか、きずあとがあるとか。そういう、めじるしになるようなものがあったら、いうがいい」
「・・・いいえ。それがなにもありません」
おこまは、くやしそうに首をよこにふりました。
「では、おしず。そちはどうじゃ?」
おしずもざんねんそうに、首をふりました。
「なんにもございません」
「そうか」
越前守(えちぜんのかみ)はうなずいて、
「では、わしがきめてやろう。おしずはたいちの右手をにぎれ。おこまはたいちの左手をにぎるのじゃ。そして引っぱりっこをして、かったほうを、ほんとうの母親にきめよう。よいな」
「はい」
「はい」
ふたりの母親は、たいちの手を片方(かたほう)ずつにぎりました。
「よし、引っぱれ!」
越前守(えちぜんのかみ)の合図で、二人はたいちの手を力いっぱい引っぱりました。
「いたい! いたい!」
小さいたいちは、両方からグイグイ引っぱられて、ひめいをあげてなきだしました。
そのとき、ハッと手をはなしたのは、おしずでした。
おこまはグイッと、たいちをひきよせて、
「かった! かった!」
と、大よろこびです。
それをみて、おしずはワーッと、なきだしてしまいました。
それまで、だまってようすをみていた越前守(えちぜんのかみ)は、
「おしず。おまえはまけるとわかっていて、なぜ、手をはなしたのじゃ?」
と、たずねました。
「・・・はい」
おしずは、なきながらこたえました。
「たいちが、あんなにいたがってないているのをみては、かわいそうで、手をはなさないではいられませんでした。・・・おぶぎょうさま。どうぞおこまさんに、たいちをいつまでもかわいがって、しあわせにしてやるように、おっしゃってくださいまし」
「うむ、そうか」
越前守(えちぜんのかみ)は、やさしい目でうなずいてから、しずかな声でおこまにいいました。
「おこま、いまのおしずのことばをきいたか?」
「はいはい、ききました。もちろん、この子はわたしの子なのですから、おしずさんにいわれるまでもありません。うんとかわいがってやりますとも。それにわたしは、人のむすこをとりあげて、自分の子だなんていう、大うそつきとはちがいますからね。だいたい、おしずさんは」
「だまれ! おこま!」
越前守(えちぜんのかみ)は、とつぜんきびしい声でいいました。
「おまえには、いたがってないている、たいちの声がきこえなかったのか! ただ勝てばいいと思って、子どものことなどかまわずに手を引っぱったおまえが、ほんとうの親であるはずがない! かわいそうで手をはなしたおしずこそ、たいちのほんとうの親じゃ。どうだ、おこま!」
越前守(えちぜんのかみ)のことばに、おこまはまっさおになって、ガックリと手をつきました。
「もうしわけ、ございません!」
おこまは、自分がたいちをよこどりしようとしたことを、はくじょうしました。
「おかあさん!」
「たいち!」
たいちはおしずのむねに、とびこみました。
「お奉行(ぶぎょう)さま、ありがとうございます。ほんとうに、ありがとうございます・・・」
おしずは越前守(えちぜんのかみ)を、おがむようにしておれいをいいました。
「うむ、これにて、一件落着!」
おしまい
| 福娘のサイト 366日への旅 |
毎日の素敵な記念日をイラスト付きで紹介。 |
毎日の誕生花を花写真付きで紹介。 |
| きょうの誕生日・出来事 有名人の誕生日やその日の出来事と性格判断 |
| 福娘のサイト 子どもの病気相談所 |
| 子どもの病気相談所 病気検索と対応方法、症状から検索するWEB問診 |
| 福娘のサイト 世界60秒巡り |
| 世界60秒巡り 世界の国旗・国歌・国鳥・観光名所などを紹介。 |
| 世界遺産巡り 日本と世界の世界遺産を写真付きで紹介。 |
| 都道府県巡り 47都道府県の豆知識。 県章、県鳥、県花、観光名所など。 |