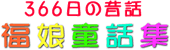| 4月26日の豆知識 366日への旅 |
ふろの日 |
えびね |
| きょうの誕生日・出来事 1971年 田中直樹 (芸人) |
| 4月26日の童話・昔話 福娘童話集 |
| きょうの日本昔話 あき寺の大入道 |
| きょうの世界昔話 月の見ていた話十四夜 |
テングと旅をした男 |
| きょうのイソップ童話 ネズミと牡ウシ |
| きょうの江戸小話 貧乏神のご開帳 |
4月26日の広告 |
4月26日の日本民話
テングと旅をした男
滋賀県の民話 → 滋賀県情報
むかしむかし、比叡山(ひえいざん)にあるお寺の修理(しゅうり)に立ちあっていた、木内兵左衛門(きのうちひょうざえもん)という若い侍(さむらい)が、とつぜん行方不明になりました。
兵左衛門(ひょうざえもん)はお酒が好きで、遊びも好きだったので、かってに山をおりて町にでもいったのだろうと、だれもが思っていました。
ところが、兵左衛門がはいていたぞうりが、お寺の玄関先(げんかんさき)と内庭(うちにわ)に片方ずつ落ちていたのです。
もっとさがしてみると、へし曲げられた刀とひきさかれた帯が見つかったので、たいへんなさわぎになりました。
「兵左衛門は玄関からでようとして、だれかにひきずられて内庭をぬけ、山の中へつれていかれたのだろう」
「刀を曲げるなんて人間ではない。まさか、テングにさらわれたのではあるまいな」
もう日は暮れて、あたりはまっ暗です。
工事の仲間も一緒に火をたいて、兵左衛門の事を心配していると、大工(だいく)の若者が、
「人の声がするぞ」
と、いって、暗やみの中へ走っていきました。
するとお堂の屋根の上で、羽のあるあやしい者が立っていて、下へおろしてくれというのでした。
よく見るとそれは、行方不明になっていた兵左衛門で、羽に見えたのはやぶれた雨傘(あまがさ)でした。
はしごをかけて屋根からおろされた兵左衛門は、とてもつかれたような荒い息をしています。
兵左衛門の話によると、夕方に名前を呼ばれたので玄関まで出ていくと、黒い衣を着た若いお坊さんが立っていたというのです。
お坊さんは顔が赤く、みだれた長い髪の毛を地面までたらしていました。
そして、
「ちょっと、そこまできてくれぬか」
と、いうなり、兵左衛門の手を強い力でつかみ、内庭のほうへひっぱって行ったのです。
兵左衛門は刀に手をかけましたが、すぐにうばいとられて曲げられてしまいました。
それからあばれる兵左衛門をかつぎあげると、お堂の屋根の上へほうりあげたというのです。
屋根の上には、赤い衣を着た鼻の高い大きなテングがいて、
「いいところへ、つれていってやる」
と、足の下にある丸いお盆のようなものにのるようにいいました。
兵左衛門が足をかけると、そのお盆はふわりと宙にうかびあがり、兵左衛門はテングと一緒に山をこえ、海をこえて、テングの仲間たちがすむ山々をめぐりました。
そしてたったいま、お堂の屋根の上にもどってきたというのでした。
「のどがからからじゃ。酒がのみたい」
と、兵左衛門がいうので、宿へもどってお酒をやると、どんぶりで五杯もたてつづけにのみほし、宿がゆれるほどの大いびきをかいて四日間もねむりつづけたという事です。
おしまい
| きょうの日本民話 ミニカレンダー |
||||||
| << 4月 >> | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 福娘のサイト | ||||||
| 366日への旅 毎日の記念日・誕生花 ・有名人の誕生日と性格判断 |
||||||
| 福娘童話集 世界と日本の童話と昔話 |
||||||
| 子どもの病気相談所 病気検索と対応方法、症状から検索するWEB問診 |
||||||
| 世界60秒巡り 国旗国歌や世界遺産など、世界の国々の豆知識 |
||||||