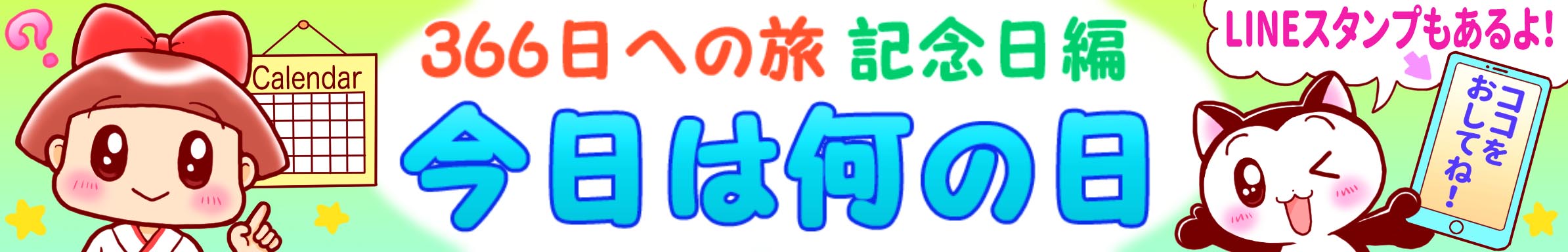| 3月3日の豆知識 366日への旅 |
| きょうの記念日 雛祭り(ひなまつり) |
| きょうの誕生花 花桃(はなもも) |
| きょうの誕生日・出来事 1958年 栗田貫一 (タレント) |
| 恋の誕生日占い 新しい物好きで、新情報の発信元 |
| なぞなぞ小学校 赤ちゃんでも指でつまめるビルは? |
| あこがれの職業紹介 スキーインストラクター |
| 3月3日の童話・昔話 福娘童話集 |
| きょうの日本昔話 タヌキの糸車 |
| きょうの世界昔話 不思議なリンゴの木 |
| きょうの日本民話 魚石 |
| きょうの日本民話 2 カワウソのいたずら |
| きょうのイソップ童話 王さまライオン |
| きょうの江戸小話 オオカミと山犬の違い |
| きょうの百物語 カエルの恩返し |
366日への旅> 今日は何の日 > 3月の記念日 > 雛祭り(ひなまつり)
3月3日 ひなまつり

記念日イメージキャラ 福ちゃん イラスト「ぺんた」 ※無断転載禁止
ひな祭りとは、平安時代の京都の風習だった子供の無病息災を願う上巳の節句(じょうみのせっく)と、ままごとの遊びが江戸時代初期に融合し、女の子のお祭りになったといわれています。
ひな祭りという呼び名は、小さな人形で「ままごと遊び」することを「ひいな遊び」と呼んでいたのが語源です。
はじめは京都の上流階級の家だけの行事でしたが、しだいに民間の行事となり、やがては地方へとひろまっていきます。
ひな祭りは江戸時代中期にかけて年々盛んになり、人形やひな壇もどんどん派手になっていきました。
当時は等身大の人形をかざったひな壇もあったといいます。
ですが、1721年(享保6)に、ぜいたくな生活を規制する当時の江戸幕府によって、ひな人形の大きさは24cm以下とさだめられました。
ひな祭りのことを別名で「モモの節句」といいますが、それは当時の旧暦の3月3日は、現在の4月上旬にあたり、ちょうどモモの花も開くころだったからです。
また江戸時代、ひな祭りの日には、銭湯でモモの葉をお風呂に入れた「桃の湯」に入るのが流行していました。
昔話の桃太郎が鬼を退治するように、植物のモモには災いをおいはらう効能があると信じられていたからです。
みなさんも、ひな祭りにはモモの入浴剤で「桃の湯」を楽しんではいかがでしょうか。

桃の節句に関する昔話
(香川県の民話)
カエルの恩返し
福娘童話集より
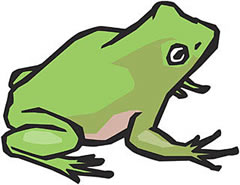
| ♪音声配信(html5) |
| 音声 ; 淺川 正寛 [声のエンタメ番組『こえんた♪』<http://koenta.seesaa.net>より] |
| ♪音声配信(html5) |
| 音声 ; スタヂオせんむ |
| ♪音声配信(html5) |
| 音声 ; 雪乃 FM79.7 京都三条ラジオカフェ 「美しい日本語を朗読で届けます!」 |
むかしむかし、ある村に、おばあさんと美しい娘が二人でくらしていました。
ある年の田植えの季節に、おばあさんは町へ買いものにでかけました。
帰りに田んぼのあぜ道を歩いていると、ヘビがカエルを追いつめて、今にものみこもうとしています。
「これこれ、なにをする。ゆるしておやり。ほしいものがあれば、わしがやるから」
カエルをかわいそうに思っておばあさんがいうと、ヘビはおばあさんの顔を見あげながらいいました。
「それなら、娘をわしの嫁にくれるか?」
おばあさんは、ヘビの言うことなどとあまり気にもとめずに、
「よしよし。わかったから、カエルを逃がしてやるんだよ」
と、返事をしてしまったのです。
すると、その年の秋もふかまったころ、若い侍(さむらい)が毎晩、娘の部屋へやってきて、夜がふけるまで娘と楽しそうに話していくようになったのです。
そんなある日の事、一人の易者(えきしゃ)が家の前を通りました。
おばあさんは易者を呼びとめると、娘にはないしょで、毎晩のようにやってくる若い侍の事をうらなってもらいました。
すると易者は、こんなことをいいました。
「ほほう。その若い侍の正体はヘビじゃ。ほうっておくと、娘の命はなくなる。娘を救いたいのなら、裏山の松の木にワシが卵をうんでおるから、その卵を侍にとってもらって、娘に食べさせるんじゃな」
おばあさんはビックリして、この話を娘にしました。
娘もおどろいて、その晩やってきた若い侍にいいました。
「実は最近、とても体がだるいのです。元気をつけるために、裏山の松の木に巣をつくっているワシの卵をとってきて食べさせてくださいな」
「よしよし、そんなことはたやすいことよ」
次の日、若い侍は裏山へいって、ワシの巣がある高い木にのぼっていきましたが、そのときいつのまにか、若い侍はヘビの姿になっていたのです。
そして木をよじのぼって、巣の中にある卵を口にくわえたとたん、親ワシがもどってきました。
親ワシはするどいくちばしで、大事な卵をくわえたヘビを何度もつつきました。
そしてヘビは頭を食いちぎられ、血だらけになって木から落ちていきました。
そのころ、あの易者がまたおばあさんの前に現われると、おばあさんに頭を下げていいました。
「実はわたしは、いつぞや田んぼのあぜ道で命をすくわれたカエルなのです。娘さんの体には、まだヘビの毒が残っております。これからは毎年、三月三日の節 句(せっく)にお酒の中に桃の花びらを浮かべてお飲みください。そうすればヘビの毒ばかりではなく、からだにたまったどんな毒もみんな消えて、きれいにな りますから」
そういうと目の前の易者の姿はたちまち消えてしまい、一匹のカエルが庭先の草むらの中へ、ピョンピョンと飛んでいったのです。
桃の節句で、お酒の中に桃の花びらを浮かべて飲むようになったのは、このときからだという事です。
おしまい
![]()
耳の日
日本耳鼻咽喉科学会が1956(昭和31)年に制定。
「み(3)み(3)」の語呂合せ。また、三重苦のヘレン・ケラーにサリバン女史が指導を始めた日であり、電話の発明者グラハム・ベルの誕生日でもあります。
耳や聴力への関心を高め、聴覚障害の予防・治療を徹底する為の記念日。
→ 日本耳鼻咽喉科学会
耳かきの日
耳かき具メーカー・レーベン販売が制定。
「耳の日」であることから。
→ レーベン販売
民放ラジオの日
日本民間放送連盟ラジオ委員会が2008(平成20)年に制定。
「耳の日」であることから。
平和の日
1984(昭和59)年の国際ペンクラブ東京大会で、日本ペンクラブの発案により制定され、翌1985(昭和60)年から世界中で実施されました。
「女の子の健やかな成長を祝う雛祭りは平和の象徴である」との考えから。
→ 日本ペンクラブ
桃の日
1999(平成11)年に日本たばこ産業(JT)が、同社の製品「桃の天然水」のPRの為に制定。
→ 日本たばこ産業
金魚の日
日本鑑賞魚振興会が制定。
江戸時代、雛祭りの時に金魚を一緒に飾ったことから。
→ 金魚のむかし話 金魚に取りつかれた若者 (福娘童話集)
→ 日本鑑賞魚振興会
結納の日
全国結納品組合連合会が制定。
結婚式の「三三九度」から。
→ 三三九度の出てくるむかし話 花嫁になりそこねたネコ (福娘童話集)
サルサの日
ダンスの一つサルサに関する活動を行っている有限会社サルサホットラインジャパンが制定。
303→サンマルサン→サルサの語呂合せ。
→ Salsa Hotline Japan
ジグソーパズルの日
ジグソーパズルメーカー会が制定。
数字の3を組み合わせるとジグソーパズルのピースの形に見えることから。
三十三観音の日
全国各地の三十三観音霊場で作る「三十三観音ネットワーク会議」が2010(平成22)年の発足会議にて制定。
女のゼネストの日
1997(平成9)年から全国各地の実行委員会が実施。
男女共同参画社会を目指し、「男女平等基本法」制定を求めて女性が立ち上がる日。
この日が女の子の節句であることから、この日に実施することになりました。
1996(平成8)年に来日したアイスランドのフィンボガドチル大統領の演説がきっかけになり制定されました。
アイスランドでは1975(昭和50)年と1985(昭和60)年に「女のゼネスト」を行い、何万人もの女性が仕事を放棄して首都レイキャビクに終結し、これを契機に初の女性大統領が誕生しました。
三の日
日本三大協会が1993(平成5)年に制定。
日本三大協会とは、「三種の神器」「日本三景」等、日本で古来より三つで括ると安定すると考えられたのはなぜか、等を研究している団体です。
| 今日誕生日 ミニカレンダー |
||||||
| << 3月 >> | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
福娘のサイト |
||||||
| 366日への旅 毎日の記念日などを紹介 |
||||||
| 福娘童話集 日本最大の童話・昔話集 |
||||||
| さくら SAKURA 女の子向け職業紹介など |
||||||
| なぞなぞ小学校 小学生向けなぞなぞ |
||||||